特定技能「建設」のすべて|要件・メリット・申請の流れをわかりやすく解説
作成日:2025年3月23日
最終更新日:2025年3月23日
日本の建設業界は少子高齢化や若年労働者の減少に伴い、長年にわたり人手不足が深刻化しています。そこで新たな活路として注目されているのが、2019年に導入された在留資格「特定技能」。建設業も14分野の一つとして認められており、優秀な外国人を即戦力として受け入れることで、現場の人手不足解消や技術伝承の強化が期待できます。
本記事では、特定技能「建設」の要件やビザ申請手続き、受け入れメリット・注意点などを詳しく解説します。外国人材の活用を検討している建設企業の皆さまは、ぜひご覧ください。
特定技能「建設」とは?導入の背景
特定技能は、人材不足が深刻な14分野で就労を認める新しい在留資格です。建設業もこの対象分野の一つで、特定技能1号と特定技能2号の2ステージに分かれています。1号は在留可能期間が通算5年であるのに対し、2号は上限なく更新でき、家族帯同も認められるのが特徴です。もっとも、建設分野に関しては特定技能2号への移行もすでに運用されており、技能実習修了者からの移行や外国人材の受け入れが進んでいます。
背景には、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化や東京オリンピック・パラリンピック需要、再開発事業の増加などがあり、建設現場での労働力確保が急務となっている点が挙げられます。国内の若年層労働力が減少する一方で、海外の技能実習生や外国人材への期待が高まり、特定技能制度を利用して安定した人材確保に乗り出す企業が増えています。
特定技能「建設」における要件と試験
特定技能で建設分野の在留資格を取得するには、以下の主な要件を満たす必要があります。
1. 建設技能試験の合格
特定技能1号として建設分野で働くためには、建設特定技能評価試験に合格する必要があります。試験は国内外で随時実施されており、型枠施工や鉄筋施工、塗装など業種別の試験が存在するケースもあります。実技や筆記試験を通じて、基本的な建設技術や安全衛生への理解を問われます。
2. 日本語能力(概ねN4相当)の証明
建設現場では日本語による指示や安全確保が重要となるため、日常会話レベルの日本語能力(概ねJLPT N4程度)が必要です。日本語能力試験(JLPT)やJFT-Basicなど、所定のテストに合格していることを証明しなければなりません。
3. 受け入れ機関の要件
外国人材を雇用する建設企業・事業所にも、下記のような条件が課されます。
- 外国人スタッフに対して日本人と同等以上の賃金水準を保証
- 登録支援機関または自社の支援計画によって生活面・就労面のサポートを実施
- コンプライアンスや安全衛生管理の徹底
特定技能2号に移行する場合は、さらに熟練技能を証明する試験合格が必要となります。特定技能2号では在留期間の更新上限がなく、家族帯同も認められるため、長期的な就労が見込める点が大きな特徴です。
特定技能「建設」を導入するメリット
建設現場に特定技能外国人を受け入れることで、以下のようなメリットが期待できます。
- 人手不足の解消:特に繁忙期や大型プロジェクトでの労働力確保が容易になる。
- 技能継承と生産性向上:ベテラン作業員と外国人スタッフの協働で技術を伝承しつつ、工期短縮や品質向上にもつながる。
- 組織の多様性と柔軟性:外国人が加わることで多様な発想が生まれ、社内コミュニケーションや士気も高まる。
- 長期的な活躍に期待:特定技能2号への移行を活用すれば、在留期間に制限なく、より安定的に人材を確保できる。
注意点と受け入れ企業がすべき対応
1. 生活支援と登録支援機関の活用
特定技能1号で外国人を受け入れる企業は、住居確保や行政手続きサポートなどの支援が義務付けられています。登録支援機関と契約してこれらの業務を委託するケースが多く、外国人スタッフが安心して生活できる環境を整えることで、離職率を下げることができます。
2. 安全衛生教育の徹底
建設業では事故を防ぐための安全衛生管理が最重要課題です。言語の壁や文化の違いによって危険が増す可能性があるため、多言語マニュアルや指差し確認など、コミュニケーションの工夫と教育プログラムを整備しましょう。
3. 給与や労働条件の整合性
外国人の賃金は日本人と同等以上が原則であり、社会保険や税金、休日などの労働条件も適切に保証する必要があります。法令違反が発覚すると、ビザ更新不可や認定取消のリスクがあるため、注意が必要です。
申請の流れ:具体的ステップ
特定技能「建設」で外国人を受け入れる際の一般的な流れは以下の通りです。
- 試験合格者の募集・面接:海外・国内問わず、建設技能試験と日本語試験を合格した候補者とマッチング。
- 雇用契約締結:労働条件や賃金などを明示した契約書を作成し、締結。
- 在留資格認定証明書(COE)の申請:受け入れ企業が必要書類を出入国在留管理庁へ提出。
- COE交付・ビザ申請:COEが交付されたら、本人が海外の日本大使館または領事館でビザ申請。
- 来日・登録支援機関によるサポート:住居探しや生活オリエンテーションなどの支援業務を開始し、実際の現場へ配属。
特定技能2号への移行とメリット
建設業は特定技能2号が適用される数少ない分野の一つです。特定技能1号で通算5年間の就労を経て、2号の技能試験に合格すれば、在留期間の上限なしで働くことが可能となり、家族帯同も認められます。長期的に優秀な人材を確保できるだけでなく、本人のモチベーションアップにつながる点も大きなメリットです。
導入事例:外国人スタッフで工期短縮に成功
ある中堅の建設会社では、多忙な現場で日本人スタッフが慢性的に不足し、工期遅延やコスト増が課題でした。特定技能1号を活用して東南アジア出身の作業員を5名受け入れたところ、すでに試験合格済みで基礎的な技術と日常会話程度の日本語力を備えており、1ヶ月程度の現場研修で作業に適応。結果として工期の遅れを取り戻し、品質保持にも成功。
企業側は登録支援機関に生活支援を委託し、現場責任者とのこまめなコミュニケーションを徹底したことで、スタッフの離職を防ぐことにも成功しました。
まとめ|特定技能「建設」で安定した人材確保と現場力向上を
特定技能「建設」は、深刻な人手不足の建設業界にとって大きな可能性を秘めています。技能実習と異なり、即戦力としての就労を前提としているため、試験合格者は一定の技術と日本語力を持っていることが期待されます。企業側には在留資格申請のサポートや生活支援義務などの負担もありますが、適切に対応することで長期的な戦力化が見込めるのが魅力です。
特定技能2号への移行で在留期間の制限がなくなることも加味すれば、優秀な外国人スタッフを継続的に雇用し、現場の技術力や企業の競争力を高められる可能性は大きいでしょう。建設現場での外国人材活用を検討している企業は、ぜひ本記事を参考に制度の活用を前向きに検討してみてください。


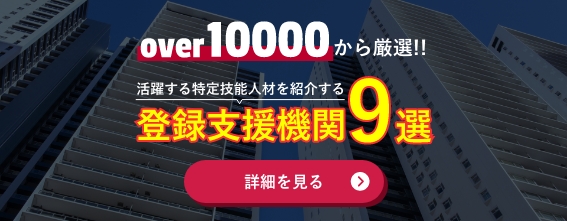
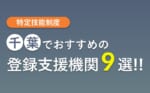
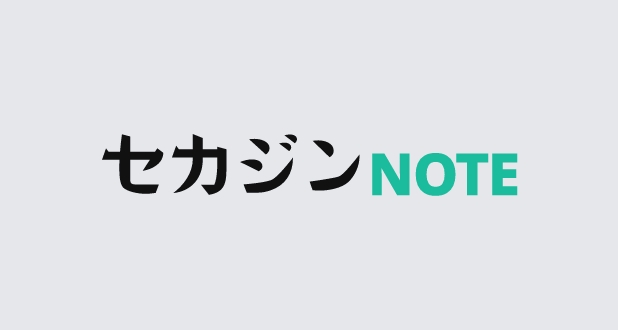
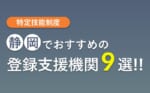
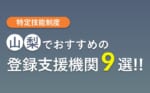
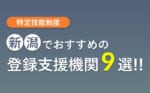
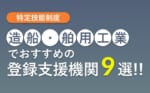
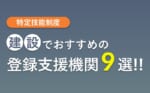
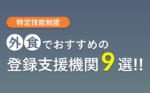
 就職説明会
就職説明会