特定技能「漁業」徹底ガイド|制度概要・要件・メリットをわかりやすく解説
作成日:2025年3月23日
最終更新日:2025年3月23日
日本の漁業は長年にわたり、少子高齢化や水産資源の変動など、さまざまな課題に直面しています。そこで注目を集めているのが、2019年に導入された「特定技能」制度です。漁業分野も14分野の一つとして指定されており、一定の技能試験や日本語試験に合格した外国人を即戦力として迎え入れることが可能です。
本記事では、特定技能「漁業」の要件やメリット、企業(漁業者)側の準備などをわかりやすく解説します。漁業の人手不足や後継者難にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
特定技能「漁業」とは?背景と概要
特定技能は、日本の人手不足が深刻な14分野で海外からの労働力を受け入れる在留資格で、漁業もその対象の一つです。技術習得を目的とする技能実習とは異なり、即戦力として就労することを前提としており、最長5年の在留期間(特定技能1号の場合)が認められます。
日本の漁業は高齢化や水産資源管理の難しさから船員不足が深刻化しており、地方の漁村では担い手の確保が大きな課題です。特定技能「漁業」の活用によって、船上作業や養殖管理、陸上での加工・出荷補助などに一定のスキルを持つ外国人を登用し、労働力を補強することが期待されています。
特定技能「漁業」の対象業務
特定技能「漁業」で認められる主な業務は、以下のように漁業や養殖業に関連する作業です。
- 漁労作業:船上での網や仕掛けの準備・操作、魚の取り込み、選別など
- 養殖業務:海面や陸上水槽での魚介類の飼育管理、給餌、疾病対策
- 陸上での水産加工:漁獲物の仕分けや加工、出荷準備(※一部工程のみ対象の場合あり)
ただし、操船や機関管理など高度な専門資格が必要な業務は範囲外となる場合が多いため、事前に制度をよく確認しておきましょう。
要件|技能試験と日本語力
特定技能「漁業」で外国人を受け入れるには、以下の条件をクリアする必要があります。
1. 漁業分野の技能試験合格
漁業特定技能評価試験に合格し、基本的な漁具や作業工程、海上の安全管理などを理解していることを証明します。試験は国内外で定期的に実施され、実技と筆記の両面から技能を確認されます。
技能実習2号を修了した外国人であれば、試験免除のケースもあり、技能実習から特定技能への移行がスムーズに進むことがあります。
2. 日本語試験(概ねN4相当)の合格
船上や陸上での安全管理や作業指示を理解し、海洋環境や気象情報を共有する必要があるため、日本語能力試験(JLPT)N4程度の能力が求められます。JFT-Basicなど同等レベルの日本語試験合格でも要件を満たします。
3. 受け入れ漁業者(企業)の要件
特定技能1号では、下記のような企業側の条件が必須です。
- 適切な賃金・労働環境:日本人と同等以上の賃金を保証し、労働条件を明示
- 生活支援計画:登録支援機関などを活用し、住居確保や行政手続きサポートを行う
- 法令遵守:不正な仲介業者を使わない、コンプライアンスを徹底
漁協や大規模漁業法人などが中心となって受け入れるケースが多く、個人経営の小規模漁業者が単独で受け入れるにはハードルが高い場合もあります。
特定技能「漁業」のメリット
特定技能を活用して外国人材を漁業分野で受け入れる主なメリットは以下の通りです。
- 人手不足の緩和:漁船の乗組員や養殖場スタッフとして一定の技能を持つ人材を確保しやすい
- 技術と生産性向上:試験合格者は基礎的な漁業技術を習得しており、現場教育コストを抑えつつ作業効率を高められる
- 長期就労が可能:特定技能1号で最長5年、技能実習2号修了者の移行によって短期間で熟練者化するケースも期待
- 多様性の導入:海外の視点や文化を取り入れ、漁業経営や加工・販売の新しいアイデアを得る
申請手続きの流れ
特定技能「漁業」での一般的な手続きは以下の通りです。
- 試験合格者の募集・面接:漁業技能試験と日本語試験に合格した外国人を漁業者が面接し、雇用契約を結ぶ。
- 在留資格認定証明書(COE)申請:雇用主が必要書類を出入国在留管理庁へ提出。登録支援機関との計画も合わせて提出。
- COE交付・ビザ申請:COE発行後、本人が居住国の日本大使館・領事館でビザを申請。
- 来日・生活支援:住居や日本語研修、職場での安全教育などを実施し、漁業に適応できるようフォロー。
漁協や大規模法人が中心となって集団申請するケースもあり、個人経営者が単独で受け入れる場合は登録支援機関の活用が重要です。
注意点|安全管理と生活環境の整備
1. 船上作業における安全と言語の壁
漁船での作業は気象条件や海況が変わりやすく、事故リスクも高いです。多言語の安全マニュアルや指差し確認の徹底を行い、外国人スタッフが適切に指示を理解できるようにしなければなりません。
2. 漁期や季節労働への対応
漁業は季節的な繁忙期と閑散期の差が激しく、労働時間や収入が安定しにくい面があります。外国人スタッフにも明確に説明し、労働基準法を守った適切なシフト管理が必要です。
3. 地域コミュニティとの共存
漁業は地域社会との結び付きが強い業種です。外国人スタッフが地域行事やイベントに参加しやすいよう配慮することで、職場定着や地域とのトラブル防止につながります。
成功事例|外国人船員で水揚げ量を安定確保
ある漁協では、高齢化に伴い若手漁師が不足し、出漁回数を減らさざるを得ない状況でした。そこで特定技能「漁業」の試験に合格した外国人を数名乗組員として採用したところ、一定の操網技術や漁具の取り扱いを既に身につけており、短期間の現場研修で即戦力化。その結果、年間の水揚げ量を従来より安定的に確保できただけでなく、若い外国人スタッフがSNSでPRするなど新たな販路開拓にもつながったとのことです。
まとめ
日本の漁業は人手不足や漁村の過疎化など深刻な問題を抱えていますが、特定技能「漁業」はこうした課題を緩和する有効な在留資格と言えます。技能試験・日本語試験を合格した外国人を即戦力として受け入れることで、漁業者は水揚げ量や生産性を安定させつつ、地域経済にも貢献できます。
一方で、安全管理や法令遵守、生活サポートなど企業・漁協側にも多くの責任が伴うため、登録支援機関や専門家を活用し、スムーズな受け入れ体制を整備することが成功の鍵です。漁業の未来を守り、発展させるためにも、特定技能を上手に活用して外国人材との協働を探ってみてはいかがでしょうか。


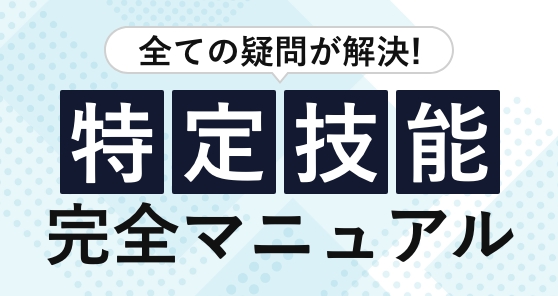
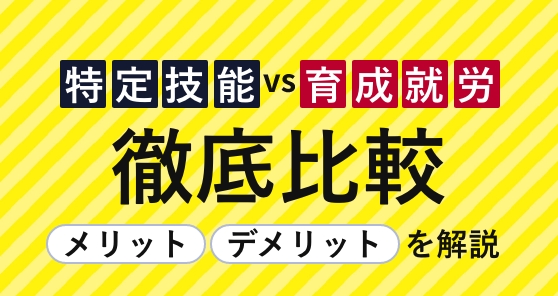
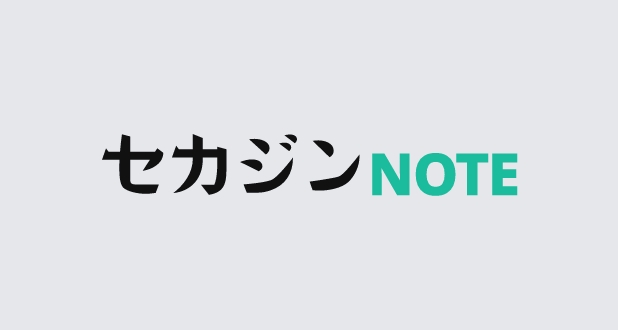
 就職説明会
就職説明会