特定技能「飲食料品製造業」徹底ガイド|要件・メリット・申請フローをわかりやすく解説
作成日:2025年3月23日
最終更新日:2025年3月23日
日本の飲食料品製造業は、少子高齢化や競争激化による人手不足が深刻化し、安定した生産体制の確保が大きな課題となっています。そんな中、2019年に導入された「特定技能」制度は、新たに外国人材を即戦力として受け入れるための在留資格として大きな注目を集めています。飲食料品製造業は14分野の一つに指定されており、一定の技能試験・日本語試験を合格した外国人を工場のラインスタッフや加工、包装などの分野で活躍させることが可能です。本記事では特定技能「飲食料品製造業」の要件やメリット、受け入れ企業(工場)側が準備すべき手続きなどをわかりやすく解説します。食品製造の人手不足を解消し、品質と効率を高めるためにぜひお役立てください。
特定技能「飲食料品製造業」とは?制度の概要
特定技能は、人手不足が深刻な14分野で外国人の就労を認める在留資格で、飲食料品製造業もその対象の一つとして指定されています。食品加工や製造ラインのオペレーション、検品や包装、出荷準備などに携わるスタッフを雇用できるのが特徴です。
従来の技能実習では“学ぶ”ことが目的であり、実習後は基本的に帰国する流れでしたが、特定技能では即戦力として長期(最長5年)就労できるメリットがあります。これにより製造ラインの安定運営や品質維持を図る企業が増えています。
特定技能「飲食料品製造業」での業務範囲
特定技能「飲食料品製造業」では、以下のような業務が想定されています。
- 食品加工・調理補助:食肉や魚介類の下処理、惣菜の製造、菓子・パン生地の調合など
- ライン作業・包装:製造ラインでの機械操作や検品、包装、ラベル貼りなど
- 衛生管理・清掃:食品工場内の衛生管理、器具の洗浄・消毒、作業場の清掃
- 品質チェック・出荷準備:完成品の検査や賞味期限表示、箱詰め・出荷ラベル貼り
ただし、バックオフィス業務(経理・総務など)や高度な開発業務などは範囲外となるため注意してください。
特定技能「飲食料品製造業」の要件
外国人がこの分野で就労するには、以下の条件をクリアしなければなりません。
1. 分野別技能試験の合格
特定技能評価試験(飲食料品製造業)に合格することが必須です。食品加工や衛生管理に関する基礎知識、製造ラインでの作業手順などが問われます。一部業務については実技試験も行われ、一定のレベルに達していることを証明しなければなりません。
技能実習2号を修了した外国人であれば試験を免除するケースもあり、実習から特定技能へのスムーズな移行が期待できます。
2. 日本語試験(概ねJLPT N4相当)の合格
食品製造ラインでは作業指示や衛生面でのルール、緊急時の連絡などで日本語のやり取りが不可欠です。そのため、日本語能力試験(JLPT)N4、またはJFT-Basic相当の日本語力が求められます。
3. 受け入れ企業(工場)側の要件
特定技能1号で外国人を採用する場合、企業側には以下のような義務があります。
- 賃金や労働条件の適正化:日本人と同等以上の待遇(給与、福利厚生など)を保証
- 生活支援計画の策定:登録支援機関の活用または自社で支援計画を設け、住居確保や行政手続きサポートを行う
- 法令遵守:不正仲介や不当な手数料の徴収を行わない、労働基準法を守るなどコンプライアンスの徹底
特定技能「飲食料品製造業」を活用するメリット
食品工場が特定技能を導入することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 人手不足の緩和:ライン作業の要員を安定確保し、繁忙期にも対応しやすい。
- 生産効率と品質向上:技能試験合格者が来るため、基礎的な食品加工技術や衛生意識が備わっている。
- 多文化共生と組織活性化:海外のスタッフが加わることで新たな視点や職場の活性化が促進される。
- 長期的戦力の確保:最長5年の在留期間に加え、技能実習からの移行で現場適応がスムーズになる場合もある。
申請手続きの流れ
特定技能「飲食料品製造業」による一般的な受け入れ手順は以下の通りです。
- 試験合格者の募集・面接:海外・国内で飲食料品製造業技能試験と日本語試験に合格した候補者を企業が募集・面接。
- 雇用契約の締結:給与や勤務時間、業務内容などを明示し、契約を結ぶ。
- 在留資格認定証明書(COE)申請:企業が必要書類を揃え、出入国在留管理庁に提出。登録支援機関を利用する場合は、その計画書も提出。
- COE交付・ビザ申請:COEが発行されたら、本人が海外の日本大使館・領事館でビザを申請。
- 来日・支援開始:住居探しや日本語研修、工場での安全教育などを行い、現場で稼働開始。
煩雑な手続きや書類作成が多いため、登録支援機関や行政書士など専門家の協力を仰ぐとスムーズです。
企業側が注意すべきポイント
1. 衛生管理と安全教育
食品工場では衛生管理が命綱です。外国人スタッフにも日本語での指差し確認や衛生ルール、作業手順を徹底し、不衛生状態やミスを防ぐ対策を行う必要があります。
2. 労働時間と繁忙期管理
季節的な需要やキャンペーンなどで製造ラインが長時間稼働する場合、労働基準法を遵守し、残業や休日出勤の管理を適正に行わなければなりません。外国人スタッフが過度な労働にならないよう配慮が必須です。
3. 生活支援とコミュニケーション
外国人が日本で暮らすのは初めてというケースも多いため、住居や行政手続き、銀行口座開設などをサポートし、職場以外でも困らない体制を整えましょう。コミュニケーションを円滑にし、定期的な面談や相談窓口を設けると離職率を低下させられます。
導入事例|外国人スタッフでライン安定稼働を実現
ある大手食品メーカーでは、繁忙期に製造ラインをフル稼働しても国内スタッフの確保が追いつかず、納期遅延が課題でした。特定技能「飲食料品製造業」に合格した外国人を数名採用したところ、既に基礎的な食品製造技術や衛生管理意識を備えており、短期間の研修で即戦力化できたといいます。結果として、ラインの安定稼働と製品リードタイム短縮を実現。企業は登録支援機関と連携し、住居サポートや日本語教室を提供することでスタッフのモチベーションを高め、離職リスクを軽減することにも成功しました。
まとめ|特定技能「飲食料品製造業」で人手不足を解消し生産性を向上
日本の食品工場やメーカーでは、人手不足が年々深刻化する中、特定技能の導入は大きな可能性をもたらします。技能試験・日本語試験を合格した即戦力人材を海外から確保し、製造ラインの稼働率を高めながら、衛生管理と品質を維持することが期待できます。
一方、外国人スタッフの受け入れには適正な労働条件の保証や生活支援、コミュニケーション対策などが必要です。登録支援機関や専門家を活用してスムーズに導入することで、企業は競争力を強化し、消費者に安全で高品質な食品を安定供給できるでしょう。
これからの製造業界で生き残るためにも、特定技能「飲食料品製造業」の活用を検討し、グローバル人材と共に更なる成長を目指してみてはいかがでしょうか。


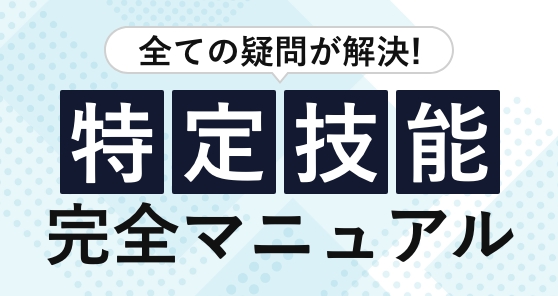
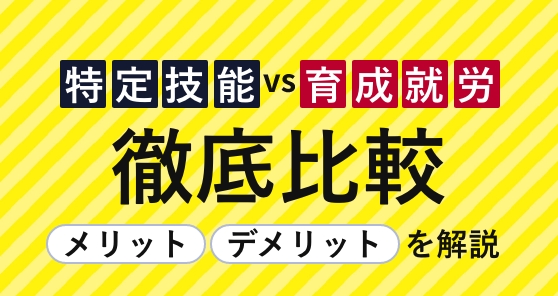
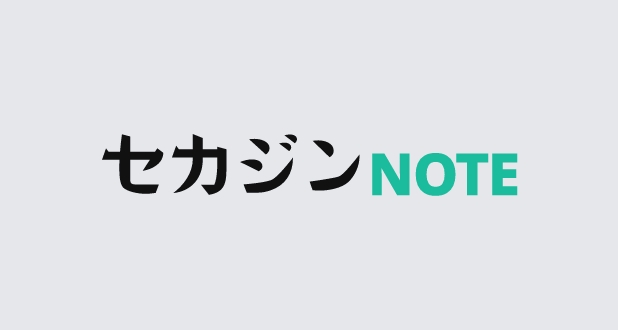
 就職説明会
就職説明会