インドネシア人の特定技能活用最前線|現状・課題・成功のポイントを徹底解説
作成日:2025年3月23日
最終更新日:2025年3月23日
日本で導入されている特定技能制度は、深刻化する人手不足を解消するための新しい在留資格です。中でもインドネシアは、政府間協定(MOC)の早期締結や技能実習を通じた人材育成の実績などから、特定技能での来日者数が増加すると期待される国の一つです。
本記事では、インドネシア人の特定技能活用状況や送り出し体制、実際に起こり得る課題とその解決策、そして企業が受け入れる際のポイントを公的情報や各種データを基に詳しく解説します。
インドネシアと特定技能制度の背景
日本の少子高齢化による人手不足解消を目的に2019年4月に導入された特定技能制度は、特に14分野(介護、ビルクリーニング、外食業など)で新たな労働力を受け入れる枠組みです。インドネシアは、技能実習生やEPA(経済連携協定)での看護・介護人材の送り出し実績が豊富で、日本との関係が深い国の一つといえます。
インドネシア政府と日本政府は、特定技能に関する協力覚書(Memorandum of Cooperation, MOC)を結んでいます。出入国在留管理庁の公表資料や在インドネシア日本大使館の情報によると、インドネシアからの送り出し機関の整備や情報共有が進められ、適正な手続きで特定技能人材を派遣する仕組み作りが行われています。
インドネシア人材の強み
- 豊富な若年層人口
インドネシアは人口約2.7億人と世界第4位の人口規模を誇り、若年層が多いのが特徴です。
そのため、海外就労への意欲が高い人材も多く、日本企業の人手不足解消に寄与すると期待されています。 - 親日感情とこれまでの実績
インドネシアは長年にわたり日本との交流があり、技能実習やEPA介護、看護師候補などで多数来日してきた実績があります。既に日本語教育の環境が整備されている点も強みです。 - 宗教的背景の理解
インドネシアはイスラム教徒が多数を占めます。企業がハラール対応や礼拝への配慮を行うことで、人材確保の際に競合他社と差別化を図ることができるでしょう。
インドネシアの特定技能制度における送り出し体制
インドネシア政府は、特定技能人材の派遣を適切に行うため、認定送り出し機関(Licensed Sending Organization)を通じて人材を送り出す仕組みを構築しています。不正な仲介業者を排除し、政府公式のスキームを通じて公正な手数料や研修プロセスを実施することが求められています。
日本政府側もインドネシア政府と連携し、送り出し前の日本語教育や分野別の技能試験対策などの情報共有を強化。「試験合格」「雇用契約締結」「在留資格認定証明書(COE)の発行」という流れを踏まえ、不当な仲介やブローカー行為を抑制する動きが高まっています。
実際に、インドネシア人が特定技能ビザを取得する場合は、日本語能力試験(N4相当)や業種別試験への合格が必須です。特定技能1号の在留期間は通算で5年までとなり、職種によっては特定技能2号へのステップアップも視野に入ります。
受け入れが多い業種と現状
インドネシア人が特定技能で来日している主な業種は以下の通りです。
- 介護
EPAや技能実習で介護に携わった経験のある人材が多く、即戦力として期待されています。 - 製造業・外食業
もともと技能実習で豊富な受け入れ実績があり、特定技能への移行もスムーズに進みやすい分野です。 - 建設・造船
体力や技術力を要する現場での需要が高く、長期就労を目指す人材にとっては特定技能2号への可能性があるため人気が高まっています。
インドネシア人材は勤勉でコミュニケーション能力に優れたケースが多く、企業からも評価が高い一方で、宗教上の制約(礼拝や食事など)や文化的習慣の違いに理解を示す体制が求められます。
インドネシア特定技能における課題と対策
1. 不正送り出し業者の存在
政府による認定制度が整備されてきているものの、ブローカーや高額な手数料を取る業者が残っているとの報告もあります。企業側は、政府公認の送り出し機関を通して人材を採用し、本人の負担を最小限に抑えた形で受け入れることが重要です。
2. 日本語力・技能試験対策
特定技能の試験に合格するためには、日常会話レベルの日本語力(N4程度)および分野別の技能試験合格が必須です。インドネシア国内では日本語教育機関の整備が進んでいますが、企業が来日前のオンライン研修や教材提供を行うなど、効果的なサポートが望まれます。
3. 文化・宗教習慣への配慮
インドネシアはイスラム教徒が多い国です。勤務中の礼拝時間確保やハラール食の対応など、企業が「日本人と同じ環境で働く」だけでなく、宗教・文化への最低限の理解を示す必要があります。
また、年中行事や祝祭日、断食月(ラマダン)への配慮を行うことで、現場での摩擦を防ぎ、離職率を下げる効果も期待できます。
4. 定着支援とキャリアパス
特定技能1号では通算5年間の就労が可能ですが、長期的に働きたい意欲があるインドネシア人材に対しては、特定技能2号や他の在留資格へのステップアップを提示することが重要です。
企業側も、勤務成績やスキル取得度合いに応じた評価制度・昇進制度を整え、将来的に熟練人材として雇用する仕組みを作ることで、優秀な人材の流出を防げるでしょう。
インドネシア人材を受け入れる企業向け成功ポイント
- 政府認定の送り出し機関と連携
インドネシア政府の公式リストに掲載されている送り出し機関を利用することで、不正ブローカーを排除し、トラブルを回避できます。 - 事前研修と日本語サポート
日本語能力試験や技能試験合格をサポートするための対策講座、オンライン学習ツールの提供を検討しましょう。 - 宗教・文化への配慮
ハラール対応食の提供や礼拝スペースの確保など、最低限の配慮を行うだけでも、インドネシア人材の安心感が高まります。 - キャリアパスの提示
特定技能2号や他の在留資格への移行、スキルアップ支援など、長期的な将来ビジョンを示すことで定着率を高められます。 - 登録支援機関(RSA)の活用
外国人材の生活・就労サポートに強い登録支援機関と提携することで、企業側の負担を減らし、外国人のストレスも軽減できます。
公的機関・一次情報を活用した最新状況
出入国在留管理庁が公表する特定技能在留者数の統計によれば、インドネシア国籍の特定技能資格者は年々増加の傾向にあります。これは技能実習からの移行や、日本語教育の普及が進んでいることが背景にあると考えられます。
さらに、厚生労働省や外務省の情報からも、インドネシアとの人材交流を促進する協議が複数回行われていることがわかります。こうした政府間の連携強化は、不透明な仲介業者を排除し、適正な送り出し・受け入れを実現する上で不可欠です。
まとめ:インドネシア人特定技能の可能性と今後
インドネシア人の特定技能活用は、若い労働力の確保と「日-インドネシア」関係のさらなる強化を同時に実現できる大きな可能性を秘めています。
技能実習の経験者を中心に、介護や建設、外食業など様々な分野で即戦力となり得る人材が増加しており、企業が受け入れ体制を整備することで安定的な戦力を確保しやすくなるでしょう。
一方で、不正ブローカーの問題や文化的ギャップへの対応など、課題も少なくありません。政府認定の送り出し機関を活用し、日本語学習サポートと宗教的配慮を徹底することで、スムーズな受け入れと定着を図ることが重要です。
企業とインドネシア人材の「win-win」の関係を築くためにも、最新の公的情報を常にチェックし、制度を正しく理解して活用することが、これからの鍵となるでしょう。


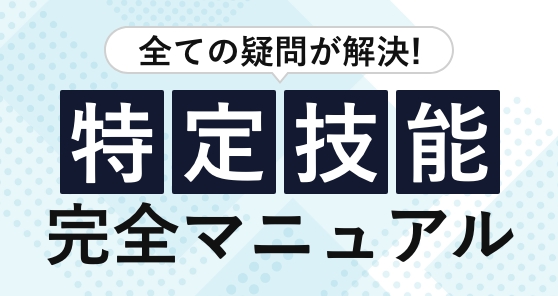
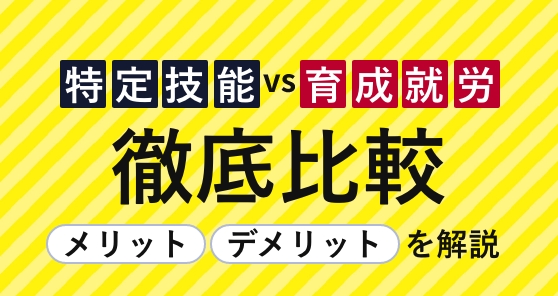
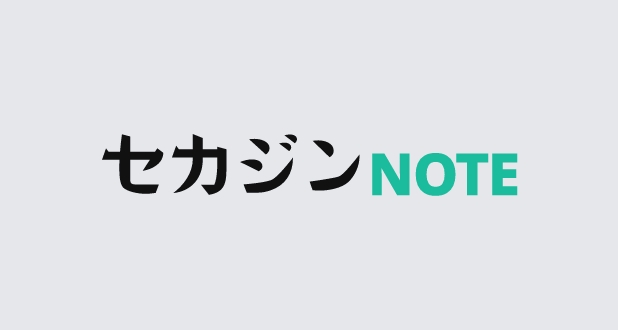
 就職説明会
就職説明会