特定技能「介護」のすべて|資格要件からメリット・申請手続きまで徹底解説
作成日:2025年3月23日
最終更新日:2025年3月23日
日本の少子高齢化が進む中、介護業界では慢性的な人手不足が深刻化しています。人材確保が最重要課題となっている現場にとって「特定技能 介護」は外国人の力を活用し、サービスの質を維持・向上するための有効な選択肢です。しかし、実際には在留資格や試験、申請手続きなど、クリアすべき課題が多く、導入を躊躇している介護施設や事業所も少なくありません。
本記事では、特定技能の介護分野にスポットを当て、要件やメリット、注意点まで徹底的に解説します。外国人採用で介護現場の人手不足を解消し、新たな戦力を確保したい方は必見です。

執筆者
セカジン運営
2014年から世界40カ国を旅し、日本と海外の暮らしの違いを肌で感じてきました。 「人がもっと自由に働ける社会をつくりたい」という思いから、外国人の在留資格や就労制度(特定技能・技人国・技能実習・育成就労など)に関する情報を発信しています。
特定技能「介護」とは?概要と導入の背景
特定技能制度は2019年4月に施行された新しい在留資格で、深刻な人材不足に対応するため日本政府が新設した仕組みです。特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、介護分野は1号で受け入れ可能となっています。従来の技能実習や経済連携協定(EPA)による受け入れ枠組みとは異なり、即戦力としての就労が目的である点が特徴です。
日本の高齢化率は世界でもトップクラスで、介護従事者の不足はますます深刻化すると予測されています。そこで、国際的に見ても伸びしろの大きいアジア・アフリカ諸国からの人材を積極的に受け入れることで、介護現場のマンパワーを確保しようというのが特定技能「介護」の狙いです。
特定技能「介護」と他の在留資格との違い
介護分野で外国人を受け入れる方法は複数存在しますが、特定技能には以下のような特徴があります。
- 技能実習:技能習得が目的。最長5年まで滞在できるが、習得後は原則帰国。
特定技能「介護」:介護職として即戦力で働く在留資格。試験合格など一定の条件を満たせば最長5年の滞在が可能。 - 経済連携協定(EPA):看護師・介護福祉士の国家資格取得を目指すための仕組み。難易度の高い国家試験合格が求められる。
- 介護ビザ(「介護」在留資格):介護福祉士の資格を日本国内で取得し、専門職として働くためのビザ。学歴・資格要件が厳格。
特定技能の介護分野は、介護福祉士資格を必須とせず、実務者研修相当+日本語能力(概ねN4)があれば従事できるため、比較的ハードルが低く受け入れられる枠組みです。特定技能2号への移行は現時点で介護分野が対象外ですが、今後の制度拡大が議論されています。
特定技能「介護」の在留資格要件
特定技能介護で外国人を受け入れるためには、候補者が以下の要件を満たしている必要があります。
1. 介護分野の技能試験合格
介護技能評価試験に合格していることが必須。これは介護の基礎知識や実技を問う試験で、海外・国内で実施されています。技能実習2号の「介護職種」を修了した場合や、過去にEPA介護福祉士候補者として相当の研修を修了した場合などは試験が免除になる場合もあります。
2. 一定レベルの日本語能力
特定技能1号は日常会話レベルの日本語力(概ねJLPT N4相当)以上が求められます。介護の場合は特に利用者とのコミュニケーションが重要になるため、「介護日本語評価試験」と「日本語能力試験(JLPT)N4相当」の合格がセットで必須とされています。
3. 受け入れ機関の基準
雇用する介護施設・事業所が適切な受け入れ体制を整えていることも要件です。具体的には、賃金水準が日本人と同等以上、雇用契約内容が明示されている、行政書士など専門家によるビザ申請支援が受けられるなど、法令遵守と外国人の権利保護を担保できる体制が求められます。
特定技能「介護」のメリット・デメリット
特定技能介護にはどのようなメリットがあるのでしょうか。併せて、導入を検討する際に知っておきたいデメリットや注意点も整理します。
メリット
- 介護人材不足を早期解消:需要が急増する介護業界で即戦力となる外国人材を確保できる。
- ハードルが比較的低い:介護福祉士資格取得を要求しないため、条件を満たした外国人が集まりやすい。
- 多様性の導入:国際色豊かな職場になることで利用者とのコミュニケーションが多様化し、チーム全体の活性化が期待される。
デメリット・注意点
- 日本語能力:N4相当とはいえ、実際に介護業務をこなすには利用者との丁寧なやりとりが必要で、研修やフォローが不可欠。
- 入国後の生活支援:住居確保や銀行口座開設などのサポートが義務化されており、企業側の負担となる。
- 将来的な定着率:最長5年で帰国する可能性があるため、長期的な人材育成や雇用維持に課題が残る。
特定技能「介護」の申請手続きと流れ
特定技能介護の受け入れを成功させるには、制度の流れをきちんと理解することが大切です。一般的な手順は以下の通りです。
- 技能試験・日本語試験に合格:応募者が介護技能評価試験と日本語能力試験をクリアしているか確認。
- 人材の選考・雇用契約締結:求人票を提示し、面接や書類審査で採用を決定。労働条件を明示した雇用契約を締結。
- 在留資格認定証明書(COE)申請:必要書類を揃え、受け入れ企業が出入国在留管理庁へ申請。
- 在留資格認定証明書の交付:交付後、本人が海外の日本大使館・領事館にてビザを申請。
- 来日・登録支援機関によるサポート:住居手配や生活オリエンテーションなど、受け入れ時の対応が義務化。
この一連のプロセスをスムーズに進めるには、登録支援機関や行政書士など専門家の助けを借りるのがおすすめです。
特定技能「介護」で成功するためのポイント
日本語研修の充実
介護業務では利用者とのコミュニケーションが欠かせません。N4合格を持っていても、実務では専門用語や敬語が必要になるため、事前研修や来日後のOJTを手厚く行うことで早期戦力化を狙えます。
職員・利用者への周知
外国人スタッフが入社する場合、日本人職員や利用者・家族への事前説明や周知が重要です。言語や文化の違い、宗教上の配慮などを踏まえた理解を促し、職場全体で受け入れ体制を整えましょう。
キャリアパスの提示
特定技能1号は最長5年間の在留ですが、その間に介護福祉士資格取得を目指す道もあります。将来のキャリアパスを提示することで、外国人スタッフのモチベーションや定着率を高めることができます。
導入事例:特定技能「介護」で業務効率アップ
ある中規模の介護施設では、夜勤や早朝シフトの人手不足が深刻化していました。外国人スタッフを特定技能介護で受け入れたところ、夜勤ローテーションに対応できる人材を確保できただけでなく、利用者とのコミュニケーションも増え、職場の雰囲気が明るくなったといいます。
登録支援機関と連携し、日本語研修や日常生活のサポートをしっかり行った結果、1年以上経過した現在もスタッフが定着し、業務効率とサービス品質の向上につながっています。
まとめ|特定技能「介護」を活用して人手不足を解消しよう
特定技能の介護分野は、人材不足が深刻な介護業界にとって大きな可能性を秘めた在留資格です。介護福祉士資格までは不要で、日常会話レベルの日本語能力と介護技能評価試験の合格で受け入れが可能となるため、多くの外国人が参入しやすいメリットがあります。その一方で、日本語研修や生活支援など企業側の努力が求められる点にも注意が必要です。
しかし、適切に導入すれば、職場の人手不足解消だけでなく多様性の向上や利用者の満足度アップなどの効果も期待できます。実際に特定技能介護を導入して成功している事例も増えており、制度の成熟に伴って今後ますます利用が広がるでしょう。外国人介護スタッフの採用を検討している施設・事業所の方は、ぜひ本記事で紹介した要点を参考に、具体的な一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。


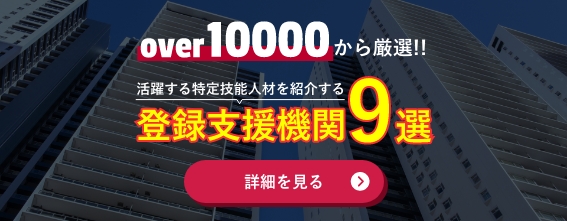
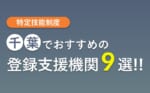
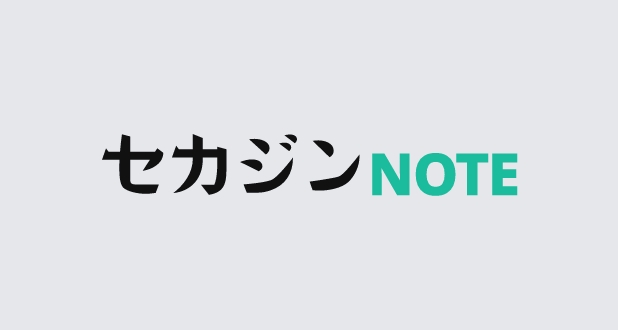
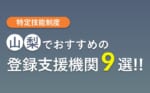
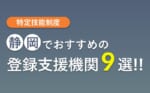
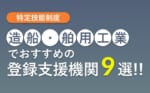
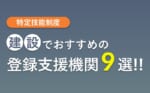
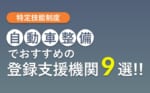
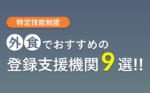
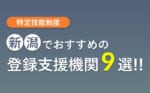
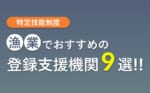
 就職説明会
就職説明会