特定技能「造船・舶用工業」徹底解説|要件・メリット・申請フローをわかりやすく紹介
作成日:2025年3月23日
最終更新日:2025年3月23日
日本の造船・舶用工業は、世界トップクラスの技術力を誇る一方、少子高齢化による人手不足や技術継承の問題に直面しています。そこで注目されているのが、2019年に導入された特定技能制度。造船・舶用工業分野も受け入れ対象の14分野に含まれており、一定の技能を持つ外国人を即戦力として雇用することが可能です。
本記事では、特定技能「造船・舶用工業」の要件や試験、企業側に求められる対応、導入メリットなどを分かりやすく解説します。船舶建造や修繕、エンジンの設計・組立などに携わる企業の皆様は、ぜひ参考にしてみてください。
特定技能「造船・舶用工業」とは?制度の概要
特定技能は、人手不足が深刻な14分野で外国人の就労を認める新しい在留資格です。造船・舶用工業もこの対象分野の一つで、外国人が試験合格などの要件を満たすことで、最大5年間(特定技能1号の場合)日本の造船所や舶用エンジンメーカーなどで働くことができます。さらに造船業は、特定技能2号への移行も可能な分野の一つとして指定されており、長期的な雇用や家族帯同が見込まれるのが特徴です。
造船・舶用工業分野は高度な技術と現場経験が求められる一方、国内の若年労働力減少により慢性的な人材不足が続いています。そこで外国人材を受け入れることで、生産ラインの補強や技術伝承を行い、企業の競争力を維持・向上する狙いがあります。
在留資格の要件|特定技能1号と2号の違い
特定技能には1号と2号の2種類があり、造船・舶用工業は1号だけでなく2号の対象にもなっています。以下、それぞれの特徴をまとめます。
- 特定技能1号:
– 在留期間は最長5年
– 家族帯同は原則不可
– 一定の技能試験・日本語試験合格が必須
– 14分野のうち造船・舶用工業を含む - 特定技能2号:
– 在留期間の上限なし(更新制限なし)
– 家族帯同が可能
– より高度な技能試験合格が条件
– 建設や造船・舶用工業など一部の分野のみ対象
特定技能2号は高度な技能が求められるため、受け入れハードルは高い一方で、長期就労と家族帯同が可能という大きなメリットがあります。1号から2号への移行を目指す外国人も多く、造船会社にとっては長期的な人材育成や技術継承が期待できる仕組みです。
試験内容|造船・舶用工業分野で必要な技能・日本語力
特定技能「造船・舶用工業」で就労する外国人には、分野別技能試験と日本語試験(概ねJLPT N4相当)への合格が求められます。実際の試験は主に以下のような内容です。
造船・舶用工業の技能試験
鉄鋼を扱う溶接や板金の基礎技術、エンジンや船体構造の理解など、造船所や舶用エンジン製造の現場で必要となる技能を評価する試験です。主に実技と筆記の両面から判断され、海外拠点や日本国内で随時実施されています。
技能実習2号を修了した外国人であれば、一部試験が免除になる場合もあるため、技能実習から特定技能へのステップアップが比較的スムーズに進むことがあります。
日本語試験(N4相当以上)
造船や安全管理においては、作業指示やコミュニケーションが重要です。そのため、日本語能力試験(JLPT)N4か、もしくはJFT-Basicなどの認定試験に合格することで日常会話レベルの日本語力を証明する必要があります。
受け入れ企業側の条件と支援義務
特定技能外国人を受け入れる企業には、適切な労働条件と生活支援を整える義務が課されます。
- 日本人と同等の待遇:賃金や休日など、外国人だからといって不当な待遇にしない。
- 在留資格申請の補助:企業が必要書類を揃え、出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書を申請。
- 登録支援機関の活用:特定技能1号で受け入れる場合、生活支援や日本語研修などを行う登録支援機関を利用するか、自社が登録支援計画を策定して支援を行う。
- 安全衛生の確保:造船業では重量物の運搬や溶接作業など危険を伴う工程があるため、安全教育や多言語マニュアルなどの配慮が不可欠。
特定技能「造船・舶用工業」を活用するメリット
人手不足に悩む造船・舶用工業で特定技能を導入するメリットは、以下のようなポイントが挙げられます。
- 熟練技術の伝承:長期的に雇用することで、外国人スタッフが高度な溶接技術や組立技術を身につけられ、世代を超えた技術継承が可能。
- 生産性向上と納期遵守:繁忙期や大規模案件での人手不足を解消し、現場の生産性を高める。納期遅延リスクを低減できる。
- 組織の国際化:海外スタッフの採用が進むことで多様な価値観が取り入れられ、新たなアイデアやイノベーションが生まれる可能性がある。
- 特定技能2号で長期雇用も可能:造船・舶用工業は特定技能2号が認められており、在留期間の上限なく働けるようになるため、企業としては安定的に人材を確保できる。
導入手続きの流れ|受け入れ準備から入国後フォローまで
特定技能「造船・舶用工業」で外国人を雇用する場合の一般的な流れは下記の通りです。
- 試験合格者の募集・面接:海外・国内で技能試験と日本語試験に合格した候補者を選考。
- 雇用契約締結:賃金・労働条件・仕事内容を明示した契約書を作成し、外国人本人と締結。
- 在留資格認定証明書(COE)申請:必要書類を揃え、出入国在留管理庁へ提出。
- COE交付・ビザ申請:COEが発行されたら、本人が海外の日本大使館・領事館でビザ申請を行う。
- 来日・受け入れ支援:住居手配や生活オリエンテーション、職場での安全教育などを実施し、スムーズな稼働へ。
1号の場合は登録支援機関を通じて生活支援を行うのが一般的です。2号へ移行する際は、追加の技能試験合格が必要となります。
成功事例|外国人材で建造スピードが向上した造船所
ある中規模の造船所では大型船舶の建造案件が重なり、人手不足で納期遅延が懸念されていました。技能実習修了者や特定技能1号合格者を数名採用したところ、溶接や塗装などの基本作業をすでに習得しており、最短2週間程度の現場研修でラインに入れるほど即戦力だったといいます。
企業側は登録支援機関と連携し、生活面のフォローや日本語研修を積極的に実施。結果的に建造スピードを維持しつつ、職場に新しい視点も取り入れられたと高い評価を得ています。
まとめ|特定技能「造船・舶用工業」で未来を切り拓く
特定技能「造船・舶用工業」は、人材不足と技術継承の課題を抱える造船産業にとって大きな希望をもたらす在留資格です。試験合格者を雇用するため、一定の技術水準が保証されており、即戦力として船体製造やエンジン組立に活躍できる可能性があります。また、特定技能2号への移行で長期雇用や家族帯同も実現し、より安定的に熟練人材を確保することができるでしょう。
一方で、安全衛生管理や法令遵守、生活支援など受け入れ企業側に求められる責任も大きいため、登録支援機関や専門家の力を借りながら、適切な体制を整えることが成功への鍵です。今後ますます高い技術力を求められる造船・舶用工業分野で、特定技能外国人材の力を活用し、業界全体の競争力と未来を切り拓いていきましょう。


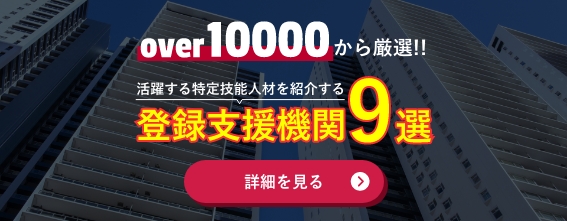
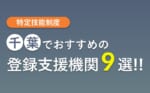
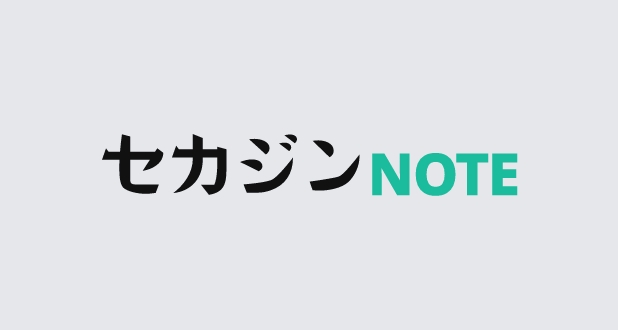
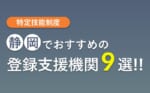
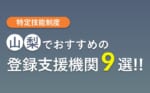
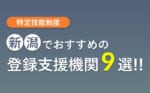
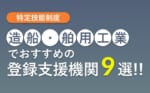
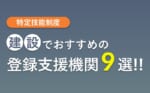
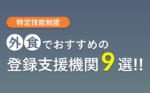
 就職説明会
就職説明会