特定技能における定期面談とは?支援機関・企業が押さえるべき実施内容と注意点
更新
特定技能外国人を受け入れる企業や登録支援機関には、「定期面談」の実施が義務づけられています。定期面談は外国人材の就労状況や生活環境を把握し、早期トラブルを防ぐために極めて重要な支援項目です。本記事では、制度上の要件、実施タイミング、面談記録の保存方法、2025年の制度改正点を含め、定期面談のすべてをわかりやすく解説します。
定期面談とは?目的と制度上の位置づけ
特定技能1号の外国人を受け入れる企業または登録支援機関は、定期的に外国人本人と面談を行い、就労・生活の実態を確認することが義務づけられています。これは義務的支援10項目の1つにあたり、制度上は「3か月に1回以上」の実施が求められます。
定期面談の主な目的は以下の通りです。
- 就労環境(労働条件・業務内容)の確認
- 生活状況(住居、交通、金銭、健康、交友など)の確認
- 不安や不満の早期発見と対応
- 本人の意思を尊重した就労継続の支援
面談の頻度と実施者の要件
定期面談は3か月に1回以上実施し、1回は外国人本人と直接対面で行う必要があります(対面以外はオンラインや電話も可)。また、原則として面談には以下の要件を満たす者が対応します。
- 登録支援機関の場合:支援責任者または支援担当者
- 企業が自社支援する場合:支援実施体制を整備したうえで、同様の担当者を置くこと
※2025年の改正により、支援担当者は外国人と同一言語での対応ができる体制が必須となっています。
定期面談で確認すべき主な項目
面談では、以下のようなチェック項目を事前に用意し、体系的に確認することが求められます。
| カテゴリ | 主な確認内容 |
|---|---|
| 労働環境 | 勤務時間、残業の有無、職務内容の変化、職場の人間関係 |
| 生活環境 | 住居、通勤、健康、金銭管理、日本語学習の状況 |
| 相談事項 | 困っていること、上司・同僚への不満、家庭問題など |
| 将来の意向 | 転職希望、2号への移行希望、帰国意向など |
記録・保存と報告の義務
定期面談の実施結果は、記録として残し、以下のように管理・報告する必要があります。
- 面談記録は5年間の保存義務あり(電子または紙)
- 記録様式は自由だが、面談日・担当者・本人確認事項を明記
- 定期届出(四半期ごと)で面談の実施状況を報告する
記録は出入国在留管理庁から監査対象になる場合があるため、漏れなく作成し保存しておくことが重要です。
企業が注意すべきポイント
形式的に面談を済ませるのではなく、「対話」によって外国人本人の状況を正確に把握することが定着率向上につながります。以下のような配慮が重要です。
- 通訳者を同席させる、または母語対応できる支援担当者が対応する
- 質問票形式ではなく、自由回答や雑談を交えたヒアリング
- 業務上の機密・立場を考慮し、上司が面談者にならないようにする
- 面談結果を社内で共有し、必要に応じて職場改善につなげる
特定技能 定期面談に関するよくある質問
Q. 面談は対面でなければならないですか?
A. 年に1回は対面必須ですが、残りはオンラインや電話でも可です。ただし、原則は直接会話による実施が望ましいとされています。
Q. 通訳がいない場合はどうすればよいですか?
A. 外国人の母語で対応できる支援担当者を配置するか、ビデオ通話等で通訳を遠隔参加させるなど工夫が求められます。
Q. 面談結果はどのように記録すればよいですか?
A. 自由様式で構いませんが、「実施日」「担当者名」「本人の確認事項・所感」は必ず記載してください。保存期間は5年間です。
まとめ|定期面談は「義務」ではなく「信頼構築」のチャンス
定期面談は単なる制度上の義務ではなく、外国人材との信頼関係を築き、長期的な雇用定着を実現するための大切な機会です。2025年の制度改正により、支援体制の質がより重視される傾向が強まっており、企業と支援機関は計画的かつ丁寧な面談の実施が求められます。
外国人本人の声に耳を傾け、継続的な職場改善とキャリア支援につなげていくことが、これからの特定技能制度の本質的な成功要因となるでしょう。


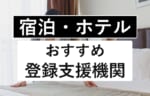
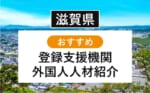
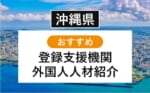
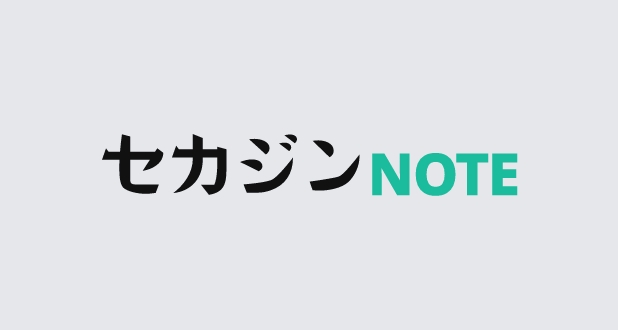
 就職説明会
就職説明会