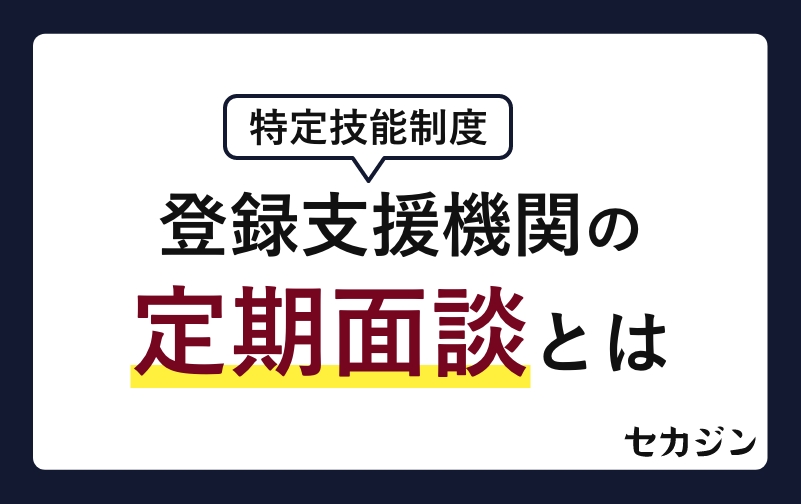
【特定技能】登録支援機関の定期面談とは?目的・頻度・面談項目と実務対応を完全ガイド
更新
「定期面談って毎月やらなきゃいけないの?」「何を聞けばいいのか分からない…」
そんな登録支援機関や企業担当者の悩みに応えるため、本記事では特定技能制度における定期面談の全体像をわかりやすく解説します。
面談の目的、実施の流れ、ヒアリング項目、トラブル対応の仕方、注意点、記録の整え方、法的義務との関係など、実務担当者が明日から実践できる内容を具体的に紹介します。制度遵守はもちろん、外国人との信頼構築に繋がる“本質的な面談”を行うためのガイドです。

外国人採用のスペシャリスト
2018年から外国人採用領域を専門とする最大手の就職し、その後、登録支援機関として合同会社エドミールを設立。技能実習、特定技能、技人国といった外国人採用にまつわる全領域に携わる稀有な専門家。のべ600名の採用支援実績があり、膨大な経験と実績から2025年度は3つの商工会議所に「外国人採用の専門家」として講師として登壇。
武藤拓矢のプロフィール …続きを読む登録支援機関における定期面談の重要性
特定技能制度において、登録支援機関が実施する「定期面談」は、外国人材の就労・生活の安定を図るうえで、極めて重要な義務的支援業務です。面談を通じて、職場環境の課題や生活上の困難を早期に把握し、必要な支援や調整につなげることが求められています。
支援の実施状況については、制度改正により定期届出(報告)は年1回に変更されましたが、現行運用においては定期面談の頻度は3か月に1回(四半期ごと)の実施が義務付けられています。
面談記録の保存は、面談の実施状況を示す重要な根拠資料であり、3か月ごとの面談実施と記録(1年以上保存)が維持されなければ、制度遵守の要件を満たさず、行政指導や登録取消のリスクも伴います。
定期面談の実施内容と流れ
面談対象者
定期面談の対象は、登録支援機関が支援しているすべての特定技能外国人です。現職の者だけでなく、支援契約中に一時的に離職している者も対象となります。
制度改正により、離職や未就労が1か月以上続く場合は「随時届出」も必要になりますが、面談義務は継続して生じます。
面談の基本的な流れ
- 面談日時・場所の調整(外国人本人および受入企業と調整)
- 面談の実施 (原則は対面、2025年4月以降はオンライン(ビデオ通話)も可能)
- 面談記録の作成と社内共有
- 必要に応じた企業へのフィードバックおよび支援内容の調整
オンライン面談の場合、面談者と外国人の同意、録画または録音記録の保存が求められます。また、オンライン実施でも五回に一度は対面面談を行うことが推奨されています。
面談の様式と証拠保全
面談記録はPDFやExcel形式で作成し、以下の情報を記載・1年以上保存してください:
- 面談日時・所要時間
- 面談者氏名・所属、使用言語・通訳の有無
- 面談形式(対面・オンライン)と場所
- 確認すべき内容:就労・生活状況、健康状態、相談事項など
- 本人の要望・相談内容
- 登録支援機関としての対応方針・フォローアップ内容
定期届出(四半期ごとの報告)で必要となるため、面談記録は定期届出の根拠資料として必ず保存してください。
面談で確認すべき具体的な内容
1. 就労状況に関するヒアリング項目
- 労働時間・残業状況が契約内容と一致しているか
- 休日取得、時間外手当の支給状況
- 業務内容の変更がないか(建前と実態の乖離)
2. 職場環境の確認
- 同僚・上司との人間関係
- いじめ・差別・ハラスメントの有無
- 労働災害や安全衛生に関する不安
3. 生活環境・精神的ストレスの確認
- 住宅・水道・ガス・電気・携帯の契約状況
- 地域生活の困りごと(役所・病院・交通など)
- 孤独感、精神的な悩み、母国との関係
4. 日本語能力・学習支援
- 職場で日本語が理解できているか
- 日本語学習の進捗状況・教材の有無
- 今後のキャリアプラン(技能試験・介護福祉士など)
定期面談での問題発覚時の対応
面談を通じて発覚する典型的な問題
- 長時間労働や未払い残業
- 職場いじめ・言語的差別
- 劣悪な住環境(高額な寮費、鍵の管理)
- 心身の不調(うつ・適応障害)
トラブル対応の基本方針
問題が確認された場合は、速やかに支援責任者・企業担当者と協議し、改善指導や是正依頼を行います。深刻な場合は、出入国在留管理局・労基署・医療機関などの公的機関と連携します。
重要:面談内容の守秘と慎重な記録
本人の発言は、プライバシーと安全を守るためにも慎重に取り扱いましょう。支援機関が外国人の信頼を得てこそ、本音が引き出せます。
定期面談を行う際の注意点
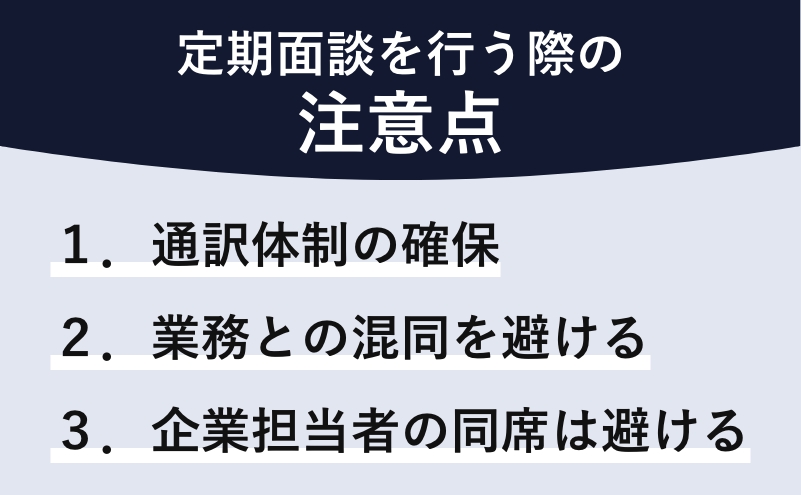
通訳体制の確保
面談は外国人本人が十分に理解できる言語で行うことが義務付けられています(出入国在留管理庁「支援実施要領」)。
日本語での意思疎通が難しい場合は、母語対応の通訳者(社内または外部)を手配することが支援機関の責務です。音声翻訳アプリなどで補完する場合でも、内容の正確性を担保することが求められます。
業務との混同を避ける
定期面談は、在留管理手続きや契約更新などの事務的な手続きと混在させず、独立した「生活支援の一環」として実施することが推奨されています。
支援対象者の悩みや不安に耳を傾ける時間として確保し、スケジュール上も分けて運用することが望ましいです。
企業担当者の同席は原則避ける
面談時に受入企業の担当者が同席すると、本人が自由に話しづらくなる可能性があるため、原則として1対1の面談が望ましいとされています(出入国在留管理庁Q&Aより)。
必要に応じて企業側にヒアリングを行う場合は、面談とは別の場面で実施するなど、情報の切り分けとプライバシーの確保に配慮しましょう。
定期面談の頻度と重要性
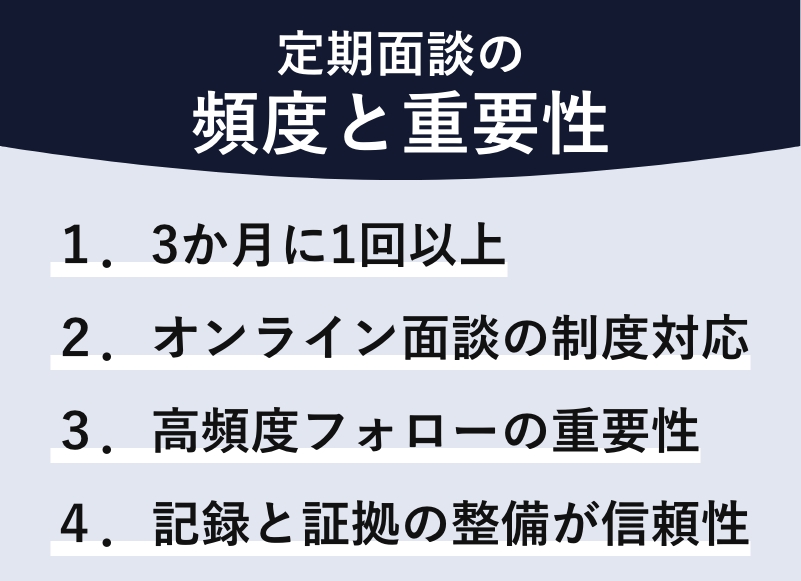
法令上の義務:3か月に1回以上
登録支援機関は、支援対象の特定技能外国人に対し、3か月に1回以上(四半期ごと)の定期面談を実施する義務があります。年4回以上の定期実施が必須であり、年1回などは制度要件を満たしません :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
オンライン面談の制度対応
これまで面談は原則対面でしたが、2025年4月1日以降、オンライン(ビデオ通話)での実施も公式に認められています。ただし、顔が見える形式での本人確認、録画・録音記録の保存、本人と監督者の同意取得が条件です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
高頻度フォローの重要性
外国人にとって、四半期ごとの定期面談は、生活・職場の悩みを相談できる心理的拠り所となります。特に来日直後や入職時の3か月間は頻度を増やすケースも多く、信頼関係構築と早期問題発見の観点からも有効です。
記録と証拠の整備が信頼性の鍵
面談結果は、日時・面談者・使用言語・形式・場所・内容・対応方針などを記録形式で保存し、最低1年以上保持する必要があります。これは制度遵守だけでなく、支援の質を担保するためにも重要です :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
登録支援機関の定期面談に関するよくある質問
Q. 定期面談は必ず対面で行わなければいけませんか?
A. 原則として対面での実施が求められていますが、2025年4月以降はオンライン面談も正式に認められています。オンライン面談を行う場合は、カメラを使用したビデオ通話形式であること、本人および面談者双方の同意を取得すること、そして録画または録音記録を1年以上保存することが条件です。音声通話のみ(電話)は不可です。
Q. 定期面談の頻度はどれくらいですか?
A. 登録支援機関は、支援対象の特定技能外国人に対して、3か月に1回以上(四半期ごと)の定期面談を実施することが義務付けられています。年4回以上の実施が必要であり、年1回では制度違反とみなされる可能性があります。
Q. 面談の実施が難しい場合、どうすればいいですか?
A. 定期面談の実施は法令上の義務であり、原則として免除は認められていません。やむを得ない理由(入院、帰国、長期出張など)がある場合は、延期理由と代替支援の内容を詳細に記録し保存し、必要に応じて出入国在留管理局へ相談することが推奨されます。
Q. 通訳を依頼する場合、費用は誰が負担しますか?
A. 通訳を登録支援機関が提供する場合、支援費に通訳費用が含まれていることが一般的です。ただし、スポット契約や一部委託の場合は企業側が別途費用を負担するケースもあります。契約前に明確に確認しておくことが大切です。
Q. 面談結果は企業に共有する必要がありますか?
A. 面談内容には個人情報が含まれるため、本人の同意なしに企業へ内容を共有することは避けるべきです。ただし、労働環境や就労条件に問題がある場合は、本人の同意を得たうえで企業に改善を促すことが望ましいとされています。
Q. 面談で記録すべき項目は何ですか?
A. 面談記録には以下の項目を網羅的に記載し、1年以上保存する必要があります:
- 面談日時・所要時間
- 面談実施者の氏名・所属
- 使用言語・通訳の有無
- 面談方法(対面・オンライン)と場所
- 就労・生活状況の確認内容
- 本人の要望・相談事項
- 対応方針・次回支援の内容
まとめ:登録支援機関の定期面談は“信頼構築”の要
登録支援機関にとって、定期面談は単なる制度対応ではなく、外国人との信頼関係を築くための最前線です。形式的に実施するのではなく、相手の立場に立って傾聴し、必要な支援に繋げていくことが求められます。
面談の質はそのまま支援の質に直結します。支援記録の整備、対応履歴の蓄積、問題の早期発見と解決への行動こそが、登録支援機関としての信頼性・継続性の根幹を支えます。
特定技能外国人が安心して日本で働ける環境を維持するために、定期面談の実施と記録を“義務”ではなく“価値”と捉えることが重要です。


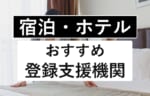
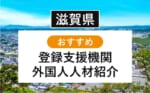
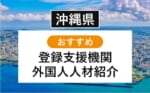
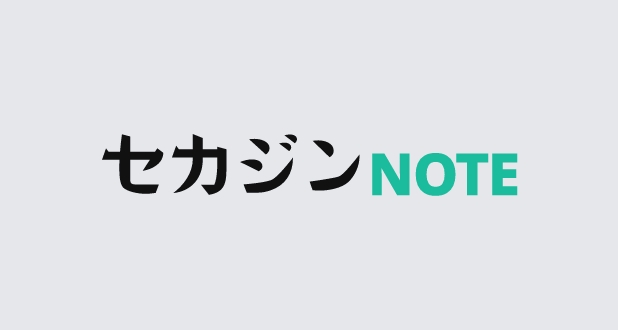
 就職説明会
就職説明会