登録支援機関の義務的支援とは?10項目の支援内容・選び方・最新制度改正も解説【2026年対応】
更新
特定技能外国人を受け入れる事業者にとって、登録支援機関による「義務的支援」は、在留資格維持や雇用の安定性を確保するうえで不可欠な制度的要件です。この支援制度は、単なる福祉的配慮ではなく、出入国在留管理庁が定める法定義務であり、外国人労働者の生活支援と職場定着を体系的に支えるものです。
本記事では、登録支援機関が実施すべき義務的支援の10項目の詳細、支援の実施手順、記録・報告義務、制度変更(2025年4月施行)に関する最新情報を網羅的に解説します。外国人材の受け入れ体制を構築・強化したい企業の人事担当者・特定技能責任者は、ぜひご一読ください。

外国人採用のスペシャリスト
2018年から外国人採用領域を専門とする最大手の就職し、その後、登録支援機関として合同会社エドミールを設立。技能実習、特定技能、技人国といった外国人採用にまつわる全領域に携わる稀有な専門家。のべ600名の採用支援実績があり、膨大な経験と実績から2025年度は3つの商工会議所に「外国人採用の専門家」として講師として登壇。
武藤拓矢のプロフィール …続きを読む登録支援機関の義務的支援とは
登録支援機関が特定技能外国人に対して行う支援には、「義務的支援」と呼ばれる必須項目があります。これは出入国在留管理庁によって制度化されており、全ての登録支援機関に対して法的に実施が求められる支援です。
具体的には、生活オリエンテーションや日本語学習支援、定期的な面談などが含まれます。支援を怠った場合、機関としての登録取消や指導対象となる可能性があるため、適切な運用が必要です。
特定技能外国人に対する義務的支援内容
特定技能外国人が日本で安定して生活・就労できるよう、登録支援機関は全10項目の支援を行うことが義務付けられています。これには、入国前の生活ガイダンス、住居探し、口座開設の支援などが含まれます。
また、外国人が困ったときに相談できる窓口の設置や、定期的な職場訪問・面談によるフォローアップも重要です。これらの支援は、単なる形式的なものではなく、外国人の就労環境と生活の安定を支える重要な制度です。
①事前ガイダンスの実施
在留資格認定証明書交付前または雇用契約締結後に、就労先や仕事内容、生活ルール、支援内容について母国語で説明する必要があります。
②出入国時の送迎
外国人が日本に入国・出国する際、空港と住居との間の送迎を支援機関が行うことが求められています。
③適切な住居の確保支援
外国人が安心して住める住居を見つけられるよう、物件探しや賃貸契約の支援、保証人探しなどをサポートします。
④生活に必要な契約支援
銀行口座の開設、携帯電話契約、ライフライン(電気・ガス・水道)の手続きなど、日本での生活に必要な契約を支援します。
⑤日本語学習の機会提供
日本での生活や職場での円滑なコミュニケーションのため、日本語学習の教材紹介や講座への案内などの学習支援を行います。
⑥相談・苦情対応体制の整備
外国人が就労や生活に関する悩みを気軽に相談できるよう、母国語で対応できる相談窓口を設けることが求められます。
⑦日本人との交流促進支援
地域のイベント参加支援や自治体とのつながりを作るなど、日本人との交流機会を促進し、孤立を防ぐ取り組みが求められます。
⑧転職・解雇時の支援
やむを得ない理由で雇用契約が終了した場合、新しい雇用先の紹介や必要書類の案内など、再就職のための支援を行います。
⑨定期的な面談と職場訪問
就労開始後3か月以内とその後3か月ごとに、本人との面談および職場訪問を行い、就労環境や生活状況の確認とフォローを実施します。
⑩関係機関への通報
外国人に対する人権侵害や法令違反があった場合は、労働基準監督署や出入国在留管理庁などの関係機関に通報する義務があります。
登録支援機関の役割と責任
法令に基づいた支援業務の実施主体
登録支援機関は、特定技能制度における「支援計画の実施主体」として、企業に代わり支援業務を担う責任ある組織です。単なる仲介業者ではなく、出入国在留管理庁から正式に登録を受けた機関であり、制度上の根幹を支える重要な立場にあります。
法令遵守と行政指導のリスク
支援計画の不履行や記録の不備、義務的支援の未実施が判明した場合、登録支援機関は出入国在留管理庁より行政指導・改善命令・登録取消といった措置を受けるリスクがあります。
そのため、支援業務には常に高いコンプライアンス意識と、適切な運用体制の構築・維持が求められます。
義務的支援の実施方法
対面・オンライン・訪問型などの実施形態
義務的支援は、内容に応じて対面・オンライン・現地訪問など複数の手段で実施可能です。特に生活オリエンテーションは、日本入国後すぐに母国語で実施することが望ましく、オンライン開催でもリアルタイムの理解確認が求められます。
記録の保存と定期報告への対応
面談記録や職場訪問記録は、毎年1回の「定期報告書」提出において重要な証拠資料となります。報告内容の不備は行政からの指導対象となるため、支援実施後の文書管理、保存期間の明確化、支援の継続性確保が必須です。
登録支援機関の選び方
対応言語・国籍の広さと現地ネットワーク
登録支援機関ごとに、対応できる外国人の出身国や言語スキルに差があります。自社が受け入れる国籍とマッチした支援実績がある機関、または海外現地送出機関と連携している登録支援機関を選ぶと、トラブル時の対応力が高まります。
料金体系と支援の内訳
支援料金の明確性も選定時の重要ポイントです。支援内容に対して「支援計画書の作成」「生活支援の実施」「定期面談の記録管理」「行政報告代行」など具体的な内訳が明記されている機関は信頼性が高く、透明性があります。
業種特化と助成金対応の有無
建設・介護・製造業など、業種に特化したノウハウを持つ登録支援機関もあります。また、外国人雇用に関する助成金や自治体補助金の申請サポートを行う機関もあるため、総合的なコストと支援品質を比較しましょう。
【2026年最新情報】定期報告が年4回から年1回に変更
制度改正の背景と企業への影響
2025年4月施行の制度改正により、登録支援機関が提出する「定期報告書」の頻度が、従来の四半期ごと(年4回)から年1回へと変更されました。
これにより、書類作成にかかる業務負担が軽減され、中小企業や支援機関にとっても運用しやすくなりました。
今後求められる運用の質と継続的な改善
報告頻度が減った一方で、報告内容の正確性と裏付け資料(面談記録・職場訪問記録・相談対応履歴など)の整備が一層重視されます。
今後は、定期報告の「質」と「適時性」が評価対象となり、支援の形式的な実施ではなく、実質的な成果が問われる運用にシフトしています。
登録支援機関の義務的支援のよくある質問
義務的支援はすべての特定技能外国人に必要ですか?
はい、原則として特定技能1号の外国人を受け入れる場合には、登録支援機関による義務的支援の提供が必要です。ただし、受入企業が出入国在留管理庁により「自己実施が可能」と認められた場合に限り、支援業務を自社で行うこともできます。
義務的支援は誰が実施してもよいのですか?
義務的支援は、登録支援機関または自己支援が認められた受入れ企業のみが行えます。外部委託する場合でも、適格な支援責任者・支援担当者の配置が必要であり、委託先にも支援実績や管理体制が求められます。
義務的支援を怠るとどうなりますか?
義務的支援の不履行、または不適切な対応が確認された場合、登録支援機関は出入国在留管理庁からの行政指導、改善命令、登録取消などの措置を受ける可能性があります。記録の不備や支援内容の不十分さもペナルティの対象となるため、注意が必要です。
登録支援機関はどこで探せばよいですか?
登録支援機関の一覧は、出入国在留管理庁の公式サイトにて公開されています。
さらに詳しく登録支援機関ごとの情報をわかりやすく知りたい方は『登録支援機関くらべナビ』の登録支援機関一覧をご確認くださいませ。
義務的支援の費用はどのくらいかかりますか?
支援費用は登録支援機関によって異なりますが、一般的に月額1万円〜2万円程度が相場とされています。契約内容によっては、初期費用や追加支援費が発生する場合もあるため、事前に見積もりを確認することが重要です。
登録支援機関の義務的支援 まとめ
登録支援機関による義務的支援は、外国人材の受け入れ・定着・活躍を実現するための不可欠な制度です。支援内容は単なる書類対応にとどまらず、生活支援・日本語学習・職場フォロー・再就職支援など、外国人が日本で安心して働くための包括的なサポートが求められます。
2026年の制度改正では定期報告の回数が見直されましたが、支援業務の実効性・記録性・法令遵守の重要性はむしろ増しています。今後も継続的な体制整備と最新制度への対応を意識し、信頼される登録支援機関の選定と連携が企業の外国人雇用成功の鍵を握ります。


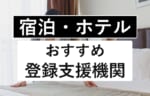
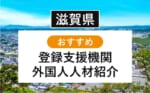
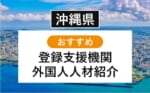
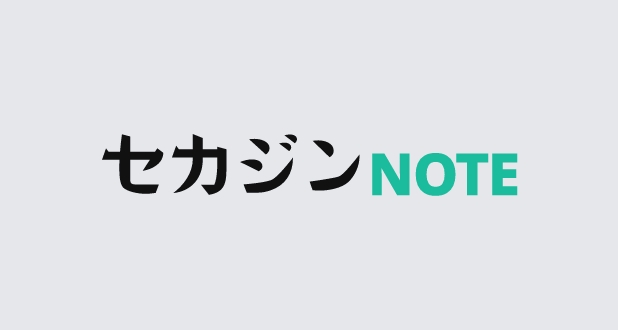
 就職説明会
就職説明会