特定技能外国人で採用できる国は16ヵ国!国別の特徴と注意点まとめ
作成日:2025年3月23日
最終更新日:
日本の特定技能制度は、2019年に始まった比較的新しい在留資格であり、少子高齢化に伴う深刻な人手不足を解消するために導入されました。対象となる14分野では、特定技能ビザを取得して就労する外国人材への期待が高まっており、その受け入れ実績も年々伸びています。
しかし「どの国からの人材が多いのか」「国によって送り出し体制や特徴が違うのか」といった疑問を抱える企業担当者や外国人本人は少なくありません。本記事では、特定技能ビザで注目される主要国の特徴や制度のポイント、申請の流れなどをわかりやすくまとめました。最新情報をしっかり把握し、特定技能の活用を検討するうえでのヒントにお役立てください。
特定技能制度とは?背景と概要
日本では近年、少子高齢化や労働力不足が深刻化しており、特に介護や外食、建設などの産業分野で人材不足が顕著となっています。こうした状況を受け、日本政府は2019年4月に新たな在留資格として「特定技能」を導入しました。この特定技能制度は、即戦力として就労できる外国人を受け入れ、日本経済の活性化や国際交流の推進を図る目的があります。
特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)には以下の2種類があります。
- 特定技能1号(特定技能1号ビザ)
- 在留期間は通算で最長5年
- 家族の帯同は原則不可(一部例外あり)
- 14の受入れ対象分野(業種)で就労が可能
- 特定技能2号(特定技能2号ビザ)
- 1号よりも熟練した技能が必要
- 在留期間の更新に上限がなく、長期滞在も可能
- 家族帯同が認められる
- 現状は建設業と造船・舶用工業の2分野のみ受け入れ可能
このように、特定技能1号と特定技能2号とでは、要件や在留期間、家族帯同の可否などが大きく異なります。特定技能制度が新設されたことで、外国人がより幅広い産業分野で活躍し、日本社会とのつながりを深めるチャンスが広がりました。
特定技能で受け入れが進む14分野
特定技能1号で受け入れの対象となっている分野は、現在以下の14分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※特定技能2号は建設業および造船・舶用工業のみ受け入れ可能となっています。
これらの分野で人手不足が顕著な状況にあり、外国人材の即戦力としての就労が求められています。
特定技能受け入れに関する日本政府と各国の「二国間協定(MOC)」とは?
特定技能制度では、日本政府と各国政府の間で「二国間協定(MOC:Memorandum of Cooperation/協力覚書)」が結ばれることが条件となっています。これは、送り出し国と受け入れ国の間で適正な人材の送り出し・受け入れの仕組みを確立し、不正な仲介や人身売買に繋がらないようにすることを目的としているものです。
二国間協定(MOC)の主な役割
- 不正ブローカーの排除・取り締まり
- 人材の円滑な送り出し・受け入れ手続き
- トラブルが起きた際の政府間調整
- 就労者の権利保護とサポート体制づくり
ここで重要なのは、協定を結んだ国の出身者のみが特定技能ビザ取得の対象となるわけではないという点です。協定を結んでいない国籍の外国人でも特定技能ビザを取得することは可能とされています。しかし、一般的には協定がある国のほうが渡航手続きや在留資格認定でのトラブルリスクが低く、受け入れ体制が比較的スムーズに整う傾向があります。
特定技能で主要な受け入れ対象国一覧
日本と特定技能に関する二国間協定(MOC)を結んでいる国は、2023年末時点で以下の国々が中心とされています。※締結のタイミングや実際の運用状況は、今後拡大・変更される場合があります。
- フィリピン
- カンボジア
- ネパール
- ミャンマー
- モンゴル
- スリランカ
- インドネシア
- ベトナム
- バングラデシュ
- ウズベキスタン
- パキスタン
- タイ
- インド
- マレーシア
- ラオス
- キルギス
現状で多くの在留者数を占めるのは、これまで技能実習制度で多くの実習生を送り出していたベトナム、フィリピン、インドネシア、ネパールなどです。また、比較的新しい国として、ウズベキスタンやパキスタンなども注目されており、政府が主体となって送り出し機関を整備している事例もあります。
なお、冒頭でも触れたように、協定未締結国でも特定技能ビザを取得できる可能性がゼロではありません。ただし協定締結国に比べると審査手続きが煩雑になったり、仲介業者の信頼性が確認しづらいなどの課題があるため、実際には協定締結国からの人材が多くなる傾向があります。
国別の特徴と動向
フィリピン
- 人口: 約1億1,000万人
- 日本への人材送り出し実績: 看護師や介護福祉士のEPA(経済連携協定)や技能実習生など、長年にわたり日本とのつながりが深い。
- 特徴: 一般的に英語力が高く、コミュニケーション面での評価が高い。また、フィリピン政府が海外での就労を推奨している面もあり、手続きが比較的整備されている。
ベトナム
- 人口: 約9,800万人
- 日本への人材送り出し実績: 技能実習生では受入れ数が最大規模となっている国の一つ。
- 特徴: 真面目で勤勉なイメージが定着しており、製造業や建設、農業など幅広い分野で活躍。ベトナム国内でも日本語教育が普及してきている。
インドネシア
- 人口: 約2億7,000万人(世界4位)
- 日本への人材送り出し実績: EPA介護福祉士候補者や技能実習生の実績がある。
- 特徴: 多民族・多文化社会であり、宗教も多様。インドネシア政府も海外出稼ぎ労働者に対して比較的開かれた姿勢を取っている。
ネパール
- 人口: 約3,000万人
- 日本への人材送り出し実績: 留学生としての日本渡航が多く、アルバイトなどを通じて日本国内で働くケースも増えている。
- 特徴: 温厚な国民性が評価されており、介護分野や外食分野などでの活躍事例が増加傾向。
ミャンマー
- 人口: 約5,500万人
- 日本への人材送り出し実績: 技能実習生としての来日者数が近年増加している。
- 特徴: 日本との政治的・経済的交流が深まっている一方、国内情勢の影響を受けやすい面もある。来日前の日本語教育環境が充実しつつある。
カンボジア
- 人口: 約1,600万人
- 日本への人材送り出し実績: 技能実習生としての受け入れが近年拡大。
- 特徴: 親日的な感情を持つ人が多いとされ、カンボジア政府も海外就労に前向き。農業や建設、製造業で需要が高まっている。
モンゴル
- 人口: 約330万人
- 日本への人材送り出し実績: 技能実習、留学などでの来日実績がある。
- 特徴: 労働人口自体は多くないが、日本語への学習意欲が高い若者が増えている。介護や建設業での就労が注目されている。
スリランカ
- 人口: 約2,200万人
- 日本への人材送り出し実績: 近年、IT人材や介護人材を中心に日本で働くスリランカ国籍の人が増えている。
- 特徴: 英語が通じる層が多く、日本企業とのコミュニケーションが円滑になりやすい。
バングラデシュ
- 人口: 約1億7,000万人
- 日本への人材送り出し実績: これから拡大が期待される国の一つ。
- 特徴: 若年層が多く、将来の労働力供給源として注目されている。工業・製造業分野を中心に需要が高まる可能性がある。
パキスタン
- 人口: 約2億2,000万人
- 日本への人材送り出し実績: 近年増加の傾向。ITエンジニアなどの高スキル人材も多い。
- 特徴: 英語教育も進んでおり、海外労働経験を持つ人も多い。日本語学習への関心も徐々に高まっている。
ウズベキスタン
- 人口: 約3,500万人
- 日本への人材送り出し実績: 特定技能制度において、新興勢力として注目されている。
- 特徴: 政府主導で人材の海外就労を奨励しており、日本への理解を深める教育プログラムも拡大中。
インド・タイ
- 人口: インド約13億9,000万人、タイ約7,000万人
- 日本への人材送り出し実績: 技能実習や高度人材ビザなど、多岐にわたる。特定技能については一部分野のみ先行して合意が進んでいる。
- 特徴: インドはITなど高度技術人材のイメージが強いが、介護や外食業などでも関心が高まりつつある。タイは観光や食品加工などで日本企業との取引が多く、交流実績が豊富。
各国からの特定技能取得者が多い業種
1. 介護
- 多くの国から人材需要が高い。特にフィリピンやベトナム、ネパールなど、英語や日本語教育が比較的行き届いている国々が強み。
- 少子高齢化の進行により、今後ますます需要が拡大すると予想される。
2. 外食業
- フィリピンやネパール、ベトナム出身者が多い。元々アルバイトなどで飲食店経験を積んだ留学生が特定技能へ移行するケースが増加。
- コミュニケーション能力が重視されるので、英語や日本語力がある人材が活躍しやすい。
3. 建設業
- ベトナムやミャンマー、カンボジアなど、これまで技能実習生として経験を積んだ外国人が多い。
- 特定技能2号への移行が可能な業種の一つで、長期で働きたい外国人にとって魅力がある。
4. 製造業(素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報など)
- ベトナムやインドネシアを中心に実習生受け入れ実績が豊富。
- 技能実習で培った技術を生かして特定技能へステップアップする流れが一般的。
5. 農業・漁業
- ミャンマーやカンボジア、ネパールなどからの人材が多く、農村地域の出身者は農業・漁業に対する理解が深い。
- 季節変動や地域特有の慣習への対応に時間がかかることもあるが、長期在留を前提とした教育環境の整備も進んでいる。
特定技能ビザ申請の主な流れ
- 日本語試験・技能試験の合格
- 特定技能1号取得には業種ごとに定められた「技能試験」と、日常会話レベルの日本語力を測る「日本語能力試験(JLPT)」N4相当以上の合格が必須。
- 介護分野の場合は「介護技能評価試験」と「日本語試験」が必要。
- 雇用先(受け入れ機関)を探す
- 日本側の企業や団体と雇用契約を結び、条件を確認する。
- 人材紹介会社や登録支援機関(RSA)を介してマッチングが進められることが多い。
- 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)
- 企業側が必要書類を整え、出入国在留管理庁に申請する。
- COE交付後、本人が居住国の日本大使館・領事館にてビザ申請。
- 入国・在留カードの受取り
- 日本入国時に在留カードが交付される。
- 在留期間内に特定技能の活動を行うことで合法的に就労が可能。
- 登録支援機関によるサポート
- 受け入れ企業が登録支援機関に支援業務を委託する場合が多い。
- 外国人労働者の生活支援や労働条件、トラブル対応などをサポート。
特定技能における国別留意点
送出機関の認定制度
- フィリピンやベトナム、インドネシアなどでは、政府が認定する送り出し機関を通じてのみ就労者を派遣するケースが多い。
- 不正ブローカーを利用しないよう、送出機関の認定証明や政府の公式リストを必ず確認することが重要。
日本語能力と文化適応
- 特定技能では「日常会話レベルの日本語力」が求められるが、国によって日本語学習環境の整備状況は異なる。
- 入国後も継続的に日本語学習が必要となるため、企業側も勉強時間や研修制度を確保する配慮が求められる。
就労後の定着支援
- 外国人が日本で長く働き続けるためには、賃金や生活環境、異文化コミュニケーションの課題を解消する必要がある。
- 食事・宗教上の習慣への理解、休日・休暇の制度、コミュニティ形成のサポートなどが重要。
特定技能と他の在留資格との違い
技能実習との比較
- 技能実習: 技能習得を目的とした制度。原則3~5年まで(延長含む)。就労は実習の一環。
- 特定技能1号: 即戦力としての就労を目的とする制度。通算5年まで就労可能。
- 特定技能2号: 更に熟練した技能が必要で、在留期間の更新に上限がない。家族帯同が認められる。
技能実習は“学ぶ・習得する”目的が強い一方、特定技能は“人手不足分野での即戦力として就労”という立ち位置にあります。そのため、技能実習から特定技能1号へ移行する外国人は増加傾向にあります。
技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)との比較
- 技術・人文知識・国際業務: 大卒程度の学歴や相応の実務経験、ホワイトカラー業務が対象。
- 特定技能: 現場作業や介護、外食、製造、建設など、幅広い分野で就労可能。学歴要件はなく、試験合格と技能レベルの証明が中心。
技術・人文知識・国際業務ビザは比較的専門性の高い業務を行う人材を対象にしており、学歴要件もある場合が多い。一方、特定技能では学歴よりも実務レベルの技能と日本語能力が重視されます。
企業側のメリットとデメリット
メリット
- 人手不足の解消
特に14分野では労働力不足が深刻であり、特定技能人材が即戦力となる。 - 多国籍・多文化の導入による活性化
組織が多様性を持つことで、新しい発想やイノベーションを生むことが期待される。 - 技能実習との組み合わせによる戦略的な人材確保
技能実習修了者を特定技能1号へ移行させることで、実習中に育んだ経験・知識を自社で継続的に活用できる。
デメリット・課題
- 言語・文化の違いへの対応コスト
日本語教育や生活サポートなど、企業側に一定の負担がかかる。 - 登録支援機関への手数料や管理コスト
特定技能では受け入れ企業が外国人をサポートする義務があり、専門の登録支援機関を利用する場合はその費用負担が発生する。 - 在留期限や試験合格など条件の厳格化
在留資格の更新時や特定技能2号への移行時には要件を満たす必要があり、人材の定着に向けたサポートが欠かせない。
特定技能で成功するポイント
- 信頼できる送り出し機関・登録支援機関を選ぶ
- 不正ブローカーを避け、政府認定の機関を利用する。
- トラブルを未然に防ぐために送出契約内容を詳細に確認。
- 日本語学習サポートを充実させる
- 事前の日本語研修だけでなく、来日後も学習を続ける環境を整える。
- 企業や仲間と実践的に会話する機会を多く設ける。
- 生活面のフォロー体制
- 住宅探し、銀行口座の開設、携帯電話の契約など、日本での生活基盤を整えるサポートが大切。
- 宗教・食習慣、休日・余暇の過ごし方についても理解を深める。
- キャリアパスを提示する
- 特定技能1号から2号への移行や、他の資格取得など、長期的な視点で人材を育成する。
- スキルアップの機会(社内研修、資格取得支援など)を提供し、モチベーション向上につなげる。
- コミュニケーションの土台づくり
- 上司や先輩、同僚とのコミュニケーション手段を多様化し、言葉の壁を低くする工夫をする。
- 定期面談や相談窓口を設置して、小さな悩みや不安も早期に共有。
今後の展望とまとめ
日本の特定技能制度は、まだ誕生して数年という新しい在留資格ですが、すでに多くの外国人材が14分野を中心に活躍し始めています。少子高齢化・人口減少が進む日本において、彼らが労働力としてだけでなく、多文化共生社会を築く重要なパートナーとなっているのは間違いありません。
- 今後予想される変化
- さらに多くの国との二国間協定締結が進み、特定技能ビザの対象国・人数が増える。
- 特定技能2号の対象分野拡大が議論され、家族帯同や長期在留が可能となる業種が増える可能性。
- デジタルトランスフォーメーション(DX)と人手不足対策の両輪で、人材ニーズや就労形態が変化。
- 企業・地域社会に求められること
- 受け入れ体制のさらなる整備(日本語教育、生活支援、職場環境改善)
- 外国人と日本人が相互理解を深めるためのコミュニケーション強化
- 外国人が安心して長く働ける環境づくり(公正な賃金、キャリア形成支援、地域コミュニティとの連携)
日本が外国人と共に成長を続けていくためには、特定技能制度の活用が不可欠と言えるでしょう。特に「特定技能 国」という視点で見れば、各国の特徴や送り出し体制を把握し、適切にマッチングを行うことで、企業・外国人双方にメリットのある雇用関係を築くことができます。
制度開始からまだ日が浅いので、運用に関する法改正やガイドラインの見直しも頻繁に行われる可能性があります。最新情報を常にチェックし、信頼できる専門家や登録支援機関のサポートを受けることが、企業側にも外国人求職者側にも重要なポイントとなるでしょう。
最後に、特定技能を通じて来日する外国人は、労働力としてだけでなく、日本社会に新しい価値観や文化をもたらす存在です。彼らが安心して働き、日本の生活や文化を楽しむことで、より良い国際交流が生まれ、日本全体の魅力や活力が高まることが期待されます。「特定技能 国」というキーワードが示すように、どの国からどのような人材が来日し、どの分野で活躍しているのかを知り、それを企業や地域、そして日本社会全体で支えていくことこそが、これからの時代の新しい常識になっていくのではないでしょうか。
まとめ
- 特定技能ビザは日本の労働市場の人手不足を解消するため2019年に導入された新しい在留資格。
- 14分野の「特定技能1号」と熟練技能が必要な「特定技能2号」の2種類がある。
- 二国間協定(MOC)の締結国を中心に受け入れが進んでいるが、未締結国からも申請は可能。
- ベトナム、フィリピン、インドネシア、ネパールなどが特に多く、今後ウズベキスタンやパキスタンなど新興国からの人材増加も期待される。
- 企業側は語学や生活サポート、登録支援機関との連携など、受け入れ体制をしっかり整える必要がある。
- 外国人材側は日本語試験と技能試験合格、就労先との雇用契約締結などの条件を満たすことが前提。
- 今後は受け入れ国や対象分野が拡大する可能性があり、日本社会における外国人の存在感はますます大きくなる見込み。
「特定技能 国」という観点で情報を網羅すると、各国の送り出し体制の特徴や、日本で活躍する分野の傾向が見えてきます。特定技能制度はまだ伸びしろが大きく、企業・外国人どちらにとっても大きなチャンスとなるでしょう。今後の最新情報を追い続けながら、適切に制度を活用していくことが、win-winの関係づくりにつながるはずです。


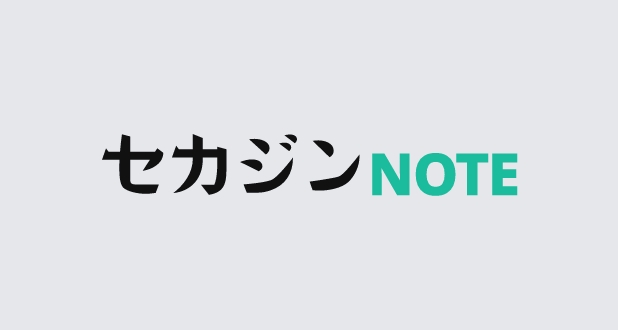
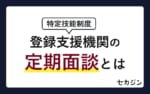
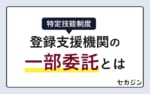
 就職説明会
就職説明会