特定技能の自社支援とは?要件・業務内容・導入メリットを徹底解説
更新
「登録支援機関に頼らず、自社で支援できないのか?」
そんな疑問を持つ企業の皆様に注目されているのが、特定技能の“自社支援”です。
外国人材に対する生活・就労支援を企業自身で実施することで、コストを抑えつつ、外国人との信頼関係を強化できます。ただし、自社支援を行うには要件を満たす必要があり、業務範囲も広範にわたるため、正しい理解が不可欠です。
本記事では、自社支援の概要から、メリット・デメリット、必要な要件、支援内容、導入手順、スケジュール感まで、網羅的に解説します。

外国人採用のスペシャリスト
2018年から外国人採用領域を専門とする最大手の就職し、その後、登録支援機関として合同会社エドミールを設立。技能実習、特定技能、技人国といった外国人採用にまつわる全領域に携わる稀有な専門家。のべ600名の採用支援実績があり、膨大な経験と実績から2025年度は3つの商工会議所に「外国人採用の専門家」として講師として登壇。
武藤拓矢のプロフィール …続きを読む特定技能の自社支援とは
「特定技能の自社支援」とは、受け入れ企業が登録支援機関に委託することなく、自ら外国人材に対する支援計画を作成・実施し、義務的支援を行う運用方法です。出入国在留管理庁が定める基準を満たすことで、自社での支援が認められます。
多くの企業では登録支援機関に業務を委託するケースが一般的ですが、社内に適切な体制が整っていれば、支援責任者や担当者を配置し、生活支援や定期面談などを自社で実施することが可能です。
近年では、義務的支援のすべてを担う「自社支援」だけでなく、一部の支援業務だけを自社で行い、その他を登録支援機関に委託する「一部委託」も増えています。初めての運用では、まずは一部業務の自社対応から始めるのが現実的です。
特定技能自社支援のメリットとデメリット
自社支援のメリット
登録支援機関に業務を委託せず、企業自らが支援業務を行うことで、コスト削減や外国人との信頼関係構築といった独自の利点があります。以下は、自社支援を導入することによる主なメリットです。
- 支援委託費用(初期費用・月額費用)を削減できる
- 自社の方針に合わせた柔軟な支援ができる
- 外国人材との関係性が強まり、定着率が向上しやすい
自社支援のデメリット
一方で、支援体制の整備や制度理解が不十分なまま自社支援を行うと、法令違反や外国人材とのトラブルにつながるリスクもあります。以下は、自社支援における注意点です。
- 支援体制を整えるための人材・時間・コストがかかる
- 法令遵守や報告義務を怠ると制度違反のリスクがある
- 複数の国籍や言語に対応する体制が必要
コスト面では魅力がありますが、体制構築と運用の責任をすべて企業が負う点に注意が必要です。
特定技能自社支援に必要な要件
支援責任者と支援担当者の配置
出入国在留管理庁が定める「支援実施基準」に従い、以下の体制が必要です:
- 支援責任者:日本人または永住者で、支援の総責任を負う者
- 支援担当者:日本語で外国人と円滑にコミュニケーションが取れる者
過去の制度違反がないこと
過去5年以内に技能実習制度や出入国管理法違反を起こしていないことが条件となります。
十分な社内体制と業務管理能力
支援実施記録の作成・保存、報告義務の履行、日本語教育や生活支援を行う体制を自社で確保する必要があります。
特定技能自社支援の業務内容
主な義務的支援内容
特定技能外国人を受け入れる企業は、以下の10項目にわたる「義務的支援」を実施する必要があります。これらはすべて自社で対応することも、一部を登録支援機関に委託することも可能です。
- ①事前ガイダンスの実施
- ②出入国時の送迎
- ③適切な住居の確保・生活に必要な契約支援
- ④生活オリエンテーションの実施
- ⑤日本語学習の機会提供
- ⑥相談・苦情への対応体制の整備
- ⑦日本人との交流促進支援
- ⑧転職・離職時の支援
- ⑨定期的な面談と職場訪問(月1回以上)
- ⑩非適正な行為を行う機関への通報
提出義務のある報告書
2025年の制度改正により、従来は3か月に1度必要だった定期報告が、現在は年1回の提出に変更されています。あわせて、支援計画に基づく履歴記録の作成と1年以上の保管も引き続き義務付けられています。
特定技能自社支援の始め方
1. 自社支援要件の確認
まずは、自社が特定技能の自社支援を行うための要件を満たしているか確認しましょう。出入国在留管理庁の「支援実施要領」では、支援体制や過去の在留資格受入実績があることなどが条件とされています。
たとえば、過去5年間に中長期在留者の受入実績がない企業は、自社支援の認可が下りにくい点に注意が必要です。
2. 支援体制の社内整備
要件を満たしていた場合は、支援業務を遂行できる社内体制を整備します。具体的には、支援責任者と支援担当者の選任が必要です。
担当者には、制度の理解だけでなく、日本語・多言語対応力や生活支援の実務能力も求められます。また、生活オリエンテーションの資料、多言語対応マニュアル、緊急時の対応フローなども社内に準備しておきましょう。
3. 支援計画書の作成・提出
支援体制が整ったら、外国人ごとに支援計画書を作成します。この書類は、在留資格の申請時に必要となるため、内容の不備や漏れがないように注意が必要です。
支援項目ごとに、誰が・いつ・どのように支援を行うかを明記し、外国人ごとに個別対応した計画を作成します。他社の支援計画書を参考にしたり、登録支援機関のひな形を活用することも効果的です。
4. 実務開始と記録保存
支援計画に基づいて支援を開始したら、各支援内容を記録として残すことが重要です。面談の日時・場所・内容、対応者、生活支援の実施状況などを、都度記録に残します。
これらの記録は最低1年間保存することが義務付けられており、出入国在留管理庁の立入検査の対象にもなります。また、2025年の制度改正により、定期報告は年1回(5月末まで)となりましたが、根拠資料として正確な記録が不可欠です。
特定技能自社支援のタイムスケジュール
| フェーズ | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| ① 要件確認 | 自社体制と制度要件の照合 | 1〜2週間 |
| ② 支援体制の整備 | 支援担当者・マニュアル・教育体制の整備 | 2〜4週間 |
| ③ 支援計画作成 | 外国人ごとの支援計画を作成 | 1週間 |
| ④ 実施開始 | 支援内容の実行、定期報告の記録 | 継続的 |
特定技能自社支援に関するよくある質問
Q. 登録支援機関を使わずに自社で支援できますか?
A. はい、支援責任者・支援体制を整えれば自社での支援が可能です。
Q. 自社支援にすると費用はどのくらい安くなりますか?
A. 登録支援機関に支払う月額1〜3万円程度の費用が不要になります。ただし、社内工数と体制整備のコストはかかります。
Q. 自社支援でも定期報告は必要ですか?
A. はい。3ヶ月に1度の定期報告書の提出は必須です。支援実施記録も保管が義務付けられています。
Q. 多言語対応が難しい場合はどうすればいい?
A. 外部の通訳サービスやオンライン翻訳ツールの活用、母語対応できる外国籍社員の起用が推奨されます。
Q. 自社支援を途中でやめて登録支援機関に切り替えることはできますか?
A. はい、可能です。ただし支援が途切れないよう、切り替えタイミングと手続きを調整する必要があります。
まとめ 特定技能自社支援
特定技能外国人の自社支援は、支援体制をしっかり整えることで費用を抑えながら、企業と外国人の信頼関係を強める有効な選択肢です。ただし、要件を満たさないままの運用や、支援記録の不備は制度違反となる可能性があるため、正しい理解と準備が不可欠です。
制度を正しく運用し、持続的な外国人雇用を実現するためにも、まずは支援責任者を中心に、自社体制の見直しから始めてみてはいかがでしょうか。


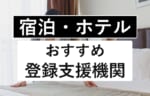
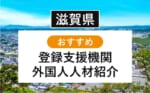
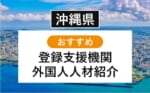
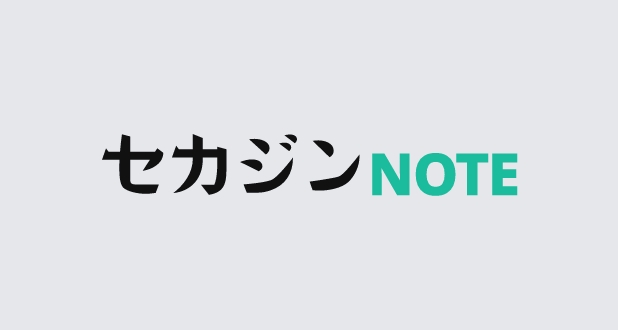
 就職説明会
就職説明会