特定技能の支援計画とは?支援内容・作成方法・記録義務を徹底解説【2026年最新】
更新
特定技能制度において、外国人材を受け入れる企業や登録支援機関には「支援計画書」の作成・実施が義務付けられています。
支援計画書は、外国人が日本で安心して働き、生活できるようにするための重要な文書です。
本記事では、支援計画の基本構成や記載すべき義務的支援10項目、記録の保存義務、変更手続きなどを2026年の最新制度に基づいて詳しく解説します。
特定技能支援計画の重要性とは
特定技能制度では、外国人材が日本で円滑に働き生活できるように、企業や登録支援機関が支援計画を策定することが義務付けられています。
この支援計画は、在留資格の取得や更新の審査にも影響する重要な書類であり、計画内容が適切であるかどうかが行政の判断材料となります。
制度上の支援責任を果たすためにも、計画は形式だけでなく、実効性と継続性が求められます。
支援計画書の基本構成
支援計画書は、特定技能外国人一人ひとりに対して個別に作成する必要があります。
書式は法務省・出入国在留管理庁の様式に準拠しており、次のような構成で記載します。
- 氏名・在留資格・在留期間など基本情報
- 支援実施者(支援責任者・担当者)の情報
- 10項目の義務的支援に関する実施内容
- 実施スケジュールおよび手段(通訳の有無など)
- 連絡体制や緊急時の対応方法
支援計画の具体的な内容
支援計画書には、以下の10項目の義務的支援内容を明確に記載する必要があります。
- ①事前ガイダンスの実施
- ②出入国時の送迎
- ③住居の確保・契約支援
- ④生活オリエンテーション
- ⑤日本語学習の機会提供
- ⑥相談・苦情対応の体制整備
- ⑦日本人との交流促進支援
- ⑧転職・離職時の支援
- ⑨定期的な面談・職場訪問
- ⑩非適正な機関への通報
それぞれに実施方法・頻度・使用言語・実施者を具体的に記載する必要があります。
支援計画の実施方法
支援計画は作成しただけでは不十分で、実施内容の記録と実行管理が重要です。
実施状況は、面談記録や相談対応履歴などとして残し、後日出入国在留管理庁から求められた際に提出できる状態にしておきましょう。
また、支援担当者と定期的にミーティングを行い、実施状況の振り返りと改善も大切です。
支援計画の変更と更新
支援計画は、外国人の状況や職場環境の変化に応じて、柔軟に見直すことが可能です。
たとえば、引っ越しに伴う住宅支援の変更や、日本語学習の進捗による支援内容の調整などが該当します。
重要なのは、変更内容を記録に残し、変更理由とその時期を明確にしておくことです。
支援計画書の提出と管理
支援計画書は、在留資格の申請時や変更時に入管へ提出する必要があります。
また、提出後も実施状況を記録として保管し、最低1年間保存することが義務付けられています。
記録が不十分だったり、支援内容が計画と乖離していた場合は、制度違反として指導の対象になることもあるため、注意が必要です。
よくある質問と相談窓口
Q. 支援計画書は誰が作成しますか?
A. 受入企業が自社支援を行う場合は企業側で作成し、登録支援機関に委託する場合は委託先が作成します。
Q. 計画に変更があった場合、再提出は必要ですか?
A. 在留資格の変更が伴わない場合は提出は不要ですが、変更内容は記録に残し、整合性を保つことが求められます。
Q. 支援記録のフォーマットは決まっていますか?
A. 明確な様式の定めはありませんが、実施内容・日時・担当者を漏れなく記録できる形式が望まれます。


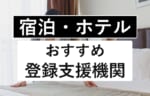
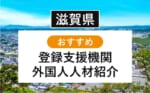
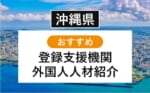
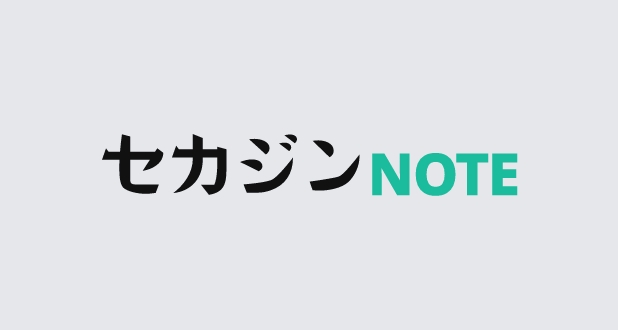
 就職説明会
就職説明会