【2026年版】特定技能ビザとは?種類・申請手続き・対象職種・企業要件を徹底解説
更新
特定技能ビザは、日本の深刻な人材不足を補うために導入された、即戦力となる外国人材の受け入れ制度です。
2026年現在、対象職種は1号で16分野、2号で13分野に対応しており、長期雇用や家族帯同も制度上可能になっています。
本記事では、特定技能ビザの種類と違い、取得要件、申請フロー、受け入れ企業側の条件、そしてよくある質問まで、制度全体を分かりやすく解説します。

外国人採用のスペシャリスト
2018年から外国人採用領域を専門とする最大手の就職し、その後、登録支援機関として合同会社エドミールを設立。技能実習、特定技能、技人国といった外国人採用にまつわる全領域に携わる稀有な専門家。のべ600名の採用支援実績があり、膨大な経験と実績から2025年度は3つの商工会議所に「外国人採用の専門家」として講師として登壇。
武藤拓矢のプロフィール …続きを読む特定技能ビザの基本知識
特定技能ビザとは、日本国内の人手不足分野において、一定の専門的技能と日本語能力を持つ外国人材を受け入れるために、2019年に創設された在留資格です。
それまでの技能実習制度と異なり、実務即戦力人材の受け入れを目的としており、制度の透明性や自由度も高く、外国人本人と企業双方にとってメリットの大きい制度となっています。
2026年現在、特定技能1号の対象分野は16分野に拡大。さらに、介護を除く13分野では特定技能2号への移行も可能となり、長期的な雇用にも対応できる仕組みが整備されています。
特定技能ビザの種類と要件
特定技能1号
特定技能1号は、各分野において基本的な業務を行う外国人を対象とした在留資格です。
- 対象分野:16分野(介護、建設、製造、農業、外食など)
- 在留期間:通算5年(4か月、6か月、1年単位で更新)
- 家族帯同:不可
- 主な要件:
- 分野別「技能評価試験」の合格
- 日本語能力試験(JLPT N4以上 または JFT-Basic)の合格
- 技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除
特定技能2号
特定技能2号は、1号よりも高度な技能を持つ熟練作業者を対象とした在留資格で、長期的な雇用が可能となる制度です。
- 対象分野:介護を除く13分野(2023年制度拡大による)
- 在留期間:更新制限なし(永住申請も可)
- 家族帯同:可(配偶者・子)
- 要件:分野別の2号技能評価試験への合格
2号は現時点では限られた国・地域でのみ試験が実施されていますが、今後の制度整備とともに拡大が進む見通しです。
特定技能ビザの申請手続き
特定技能ビザの取得は、以下の手順に沿って進めます。
- 試験の合格:日本語能力試験および技能評価試験の合格(または技能実習2号修了)
- 雇用契約の締結:受入企業との正式な契約
- 支援体制の整備:支援計画の作成(登録支援機関委託 or 自社支援)
- 在留資格認定証明書交付申請:企業側が地方出入国在留管理局へ申請
- ビザ申請・入国:外国人本人が現地大使館でビザ申請 → 入国
日本国内在留中の外国人(留学、技能実習など)であれば、在留資格変更申請による切り替えも可能です。
特定技能ビザの受け入れ企業の要件
外国人を特定技能で受け入れる企業にも、以下のような法的要件が定められています。
- 労働条件が適正(最低賃金以上、社会保険加入など)
- 日本人と同等以上の待遇が確保されていること
- 10項目にわたる義務的支援の体制があること
- 不正受け入れ歴がないこと(過去5年以内)
義務的支援には「入国時の送迎」「生活オリエンテーション」「日本語学習支援」などが含まれ、登録支援機関に外部委託することも可能です。
特定技能ビザに関するよくある質問
Q1. 特定技能1号と2号の違いは?
A. 1号は基本的な作業を行う外国人を対象に、最大5年の在留。2号は熟練技能を要する業務で、更新制限がなく、家族帯同も可能です。
Q2. すべての職種で特定技能2号は取得できますか?
A. いいえ。2026年現在、2号の対象は介護を除く13分野に限定されており、新たに追加された「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」は2号対象外です。
Q3. 試験はどこで受けられますか?
A. 各分野の試験は日本国内または海外の指定会場で実施されており、JAC(Japan Association of Certified Evaluation Organizations)や出入国在留管理庁の公式サイトで日程が公表されています。
特定技能ビザまとめ
特定技能ビザは、日本の慢性的な人手不足を補うための即戦力人材制度として、多くの企業・自治体で活用が進んでいます。
2026年現在、1号は16分野、2号は13分野に対応しており、外国人労働者の中長期雇用が現実的に可能となっています。
申請時の法令遵守や支援体制の整備は必須であり、企業側にも高い運用意識が求められます。
これから外国人材の受け入れを検討する企業は、分野ごとの試験要件・支援方法・在留条件を正しく理解し、計画的な採用・定着支援を行うことが重要です。


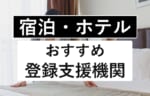
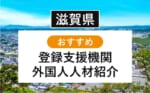
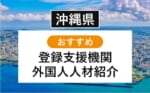
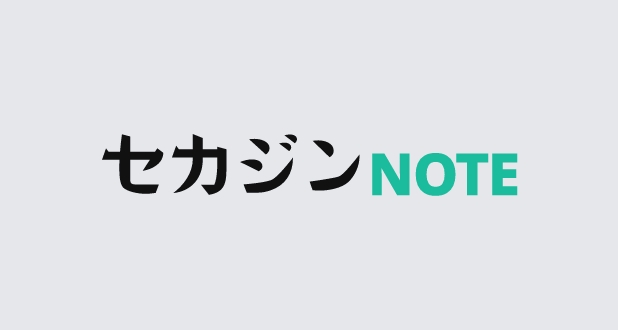
 就職説明会
就職説明会